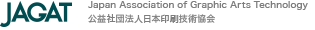本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
フォントデザインとつめ組みの功罪(1) (1999/12/8)
最近の書籍・雑誌を見ると流行のごとく「つめ組み」組版が氾濫している状況で、特にDTPによる組版に多く見られる。
本来は、文字サイズを拡大すると漢字やかな文字の字間が開き過ぎている場合にこの手法を用いるが、本文全体につめ処理を行うため漢字の字間がなくなり重なっているのが見られ、可読性が損なわれることになる。このような印刷物の編集企画者は無神経といってもよいであろう。
和文文字の漢字・ひらかな・カタカナは、全角(正方形)の仮想ボディを基準にデザインされている。したがって写植文字板やアウトラインフォントのように、一つの字母(フォント)からリニアスケーラブルに拡大すると、適正な字間を維持できない場合がある。
本文用(9ポイント~12ポイント)に使う書体は、そのサイズに適応した漢字とかなの大きさとウエイトのバランスをとり設計するのがデザインの基本である(そうでないフォントもあるが)。つまり本文組みではつめないで組むのが自然で可読性は良いことになる。
しかし本文用のフォントを拡大して使う場合はつめ処理をした方がよいが、そのような使い方は少ない。また太・特太の明朝やゴシックなどの見出し用フォントでも、拡大率が大きい場合は字間調整が必要になる(図参照)。

活字の場合は、基本的には文字サイズごとに適応した原字(種字)を彫刻する。それを基にして電胎母型がつくられ、その母型から活字を鋳造する。つまり固定ボディサイズに対するレターサイズ(字面)やウエイト(太さ)などのバランスをとっている。つまり本文用の10ポイントと見出し用の40ポイントでは字面(じづら)の大きさ(字面率)や太さは異なっている。すなわち文字サイズが大きくなっても、漢字とかなをベタ組みで字間が適正になるように字面を大きく、ふところを広げるなどの視覚調整を施している。
ところが写植になると、一つの字母から光学的手段による印字方式であるから、レンズの倍率を変えることで文字の拡大・縮小が容易になった反面、別な問題を生み出した。一つの字母から比例的にいろいろな文字サイズを生み出す方式では、自動的に字面率を変化させることは原理的に不可能である。このことは一つのアウトラインフォントを使うコンピュータ方式でも同様なことがいえる。
写植方式は、活字では不可能な組版技術を生み出した。その一つが「つめ組み」で、写植はつめ組みを可能にしたといわれた。その理由は拡大文字サイズのベタ組みでは字間の開きが目立ちすぎる。いいかえれば、まともな組版ができないということから、その対処方法として「やむを得ず」つめ組みという手法が生まれたと考えられる。