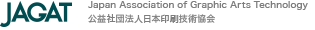本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
フォントデザインとつめ組みの功罪(2) (2000/1/21)
前回で活字母型はサイズごとに原字(種字)を彫刻して製作することを述べた。ところが活字でも手彫刻のときと異なる現象が起きたことがある。それは母型製作の量産化を図るためにベントン母型彫刻機が導入されたことである。
この方式は、パンタグラフの原理を応用したもので、一つのパターン(文字原版)を用いて小サイズから大サイズまでの母型を彫刻できる。1949年以降に大手印刷会社や母型メーカーなどが、ベントン彫刻機を模倣した国産の母型彫刻機を積極的に導入し母型製作の量産化を図った。
またこの方式は、サイズごとに手彫刻で数千字の漢字を製作する従来の母型製作方法に比して、活字母型の量産化という面で画期的なことであったが、小サイズの活字と大サイズの活字では太さもデザインも異なるわけで、一つのパターンから本文用と見出し用の母型を作ることに無理があった。
しかしパターンは原字版下から作成するので、一字一字原字デザインを必要とした。あたかもデジタルフォント作成にデザイン原字からスキャナ入力したことと同様に、原字製作に多くの時間と労力を要する。
そこで本文用の6ポイント~10ポイントまでの範囲を一種類のパターンを用い、12ポイント以上のサイズは数段階に分けてパターンを作成する方法で母型製作を行った。この機械彫刻も厳密な意味ではリニアスケーラブルに拡大・縮小するわけだから、写植やアウトラインフォントと似たような現象が起きるといえるが、拡大・縮小の格差が少ないので大きく目立つわけではない。しかも活字組版ではつめ組みができないという問題がある。
雑誌などは決められたスペース(ページ数)に、より多くの情報量を盛り込むという意図から、その手法としてつめ処理を利用することは理解できるが、つめる必要がないものはつめない方がよい。情報量を多く盛り込むということは、文字数を増やすことではなく文章表現の工夫で補えるであろう。冗長な文章構成は、単に文字数を増加させるだけになる。
つめ処理の問題を取り上げる理由は、可読性に関係するからだ。つめ処理と禁則処理を併用しジャスティファイをすると、各行の縦・横の文字の並びが揃わないため可読性が悪くなる。しかも行間が全角アキに近いような組み方では顕著である。つまり文字が横に並んでいるのか、縦に並んでいるのか一見して判別し難い。
可読性が良いとは、「早く読めること」「読みやすいこと」「誤読をしにくいこと」ということである。可読性の条件はフォントデザインにも求められる要素であるが、組み方やレイアウトに対しても必須条件である。視線が流れるように読めることが重要で、目が戸惑うようでは可読性が良いとはいえない。
見出し組みのつめ処理は効果的だが、本文用フォントが全角で漢字とかなの字面率がバランスよくデザインされたものであれば、つめる必要はないであろう。またつめ処理の場合、かなに対する「つめデータ」をもつフォントを使えば無理のないつめ処理ができる。ただしアプリケーションソフトが「つめ処理機能」をサポートしている必要がある。
適切なつめ組みは可読性を助長する要素にもなるが、過度なつめ処理は可読性を損ない、害あって益なしということになる。
次回から「フォント関連」について述べてみよう。