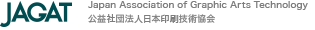本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
印刷メカニズムとフォント (2000/2/6) フォントデザインの実際(2)
フォントおよび書体デザインは、文字処理方式と印刷メカニズムに関係が深い。歴史的にみても文字処理方式により書体デザインは変化してきた。
活字組版時代に使われた文字は活字で、母型から鋳造してつくられる。写植組版時代の文字は文字盤からレンズを通して感光材料に露光される方式で、これが活字書体と異なるところである。このメカニズムの違いが書体デザインに影響を与えている。
つまり活字は凸版印刷方式の原版であり、紙の上に圧を加えるため「マージナルゾーン」というインキのはみ出し現象が起きる。これを考慮して活字デザインを行う。
これに対して写植は、主に平版印刷用(オフセット印刷)に使われるためマージナルゾーンは起きないが、写植機における光学的な露光条件やフィルム製版条件などに影響される。そのために同じ書体でも文字設計の表現効果を考えてデザインする。
文字処理方式とフォントの変化
このことはデジタル文字(電子活字)においても同じことがいえる。
当初の文字のデジタル化は、多くは活字や写植の原字を元にして行われた。電算写植の場合は印画紙に露光するというメカニズムは共通していたが、コンピュータに使われるフォントは当初ドットフォントであった。 ドットフォントの場合は、原字を基にしてボディのメッシュサイズごとにフォントを作成する。16ドット、24ドット、32ドット、48ドットなどである。これらのドットフォントは文字デザイン表現にはほど遠いもので、いかに字形を整え読みやすくするかのテクニックを要した。
しかしアウトラインフォント時代になって、文字デザインを忠実に表現できるようになったが、文字出力品質は出力装置の解像度に左右されるという問題があった。つまり300dpi、400dpi程度の低解像度の出力装置では、デザインの微妙なニュアンスが表現できない上に、曲線部分にジャギー(ギザギザ)という現象が生ずることである。
アウトラインフォントは、1つのマスターフォントから拡大・縮小が可能という利点はあるが、低解像度の小サイズ出力では量子誤差による線の太さのバラツキなどの文字品質の劣化を招く。その現象を回避するために「ヒンティング(線幅補正)」というテクノロジー」が用いられる。
現在のように、多くのプリンタやイメージセッタなどが高解像度化されている環境ではこのような問題は減少したが、タイポグラフィとしてのフォントデザインの基本はすべて共通しているものである。1つのマスターフォントが多様な出力装置やマルチメディアに利用されることを考えると、安易にフォントデザインはできない。
ところが写植組版がデジタル方式になり、文字もデジタルフォントが使われるようになった。当初のデジタル方式の出力機はCRT方式でドットフォントが使われていたが、後年ベクターフォントが用いられるようなった。このベクターフォントを数学的に曲線補完したものが、現在主流になっているアウトラインフォントである。
このように文字処理方式の変遷とともに書体デザイン、つまりフォントデザインが変化してきた。