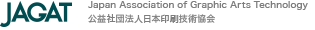本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
ポイント・システムの由来(3) (2000/8/12) 活字の大きさと高さ(2)
日本の活字の大きさ
日本における和文活字の大きさは、1869年に本木昌造がウイリアム・ガンブルの考案した号数活字のシステムを参考にした「号数制」が基本になっていた。
ガンブルはスモールパイカ(11ポイント)を5号活字としたが、本木昌造はこの11ポイントに日本の尺度にあたる鯨尺の1分をあてた。
号数活字の中心は5号活字であるが、当時は本文用としては5号(10.5ポイント)、4号(13.75ポイント)が使われていた。後年このサイズを採用したのが和文タイプライタである。また現在のワープロソフトでもこの名残があり、フォントサイズのなかに5号の10.5ポイントを、デフォルトで採用しているのは面白い現象である。
号数制は合理的にできているが、号数制の不便なことはポイント制と異なり名称と倍数関係が一致していないことである。たとえば5号(10.5ポイント)の倍は2号(21ポイント)、4号(13.75ポイント)の倍は1号(27.5ポイント)などの関係になっているため、ポイント・システムよりは直感的に判りにくい。
号数制とは異質のアメリカ式ポイント活字を初めて日本へ導入したのは、1903年東京築地活版製造所の支配人であった野村宗十郎といわれている。その後1911年に秀英舎(大日本印刷の前身)もポイント活字を製作し、ポイント活字が普及し始めてから活字の大きさの体系が入り乱れ組版上混乱が生じた。
その結果1962年に、和文活字のJIS規格が制定されポイントに統一されたが、その後も号数活字は使われていた。
活字の高さ
活字の高さは世界各国を通じてさまざまである。最も低いのは0.918インチ(23.317mm)で、最高は0.991インチ(25.171mm)などがあるが、0.918インチはイギリス・アメリカを中心に、また0.928インチはフランス・ドイツを中心にして多く使われている。
活字の高さとは、活字の足から字面までの長さをいう。活字を鋳造する場合、高さの統一と精度は絶対条件である。高さが不揃いの活字で組版されたものは版面が不均一で、印刷の際のムラトリ作業を困難にする(図参照)。

日本においても活字の高さは一定せず、0.918~0.925インチの間でまちまちである。しかしJISでは0.923インチに近い23.45mmと決めているが、活字の高さは母型の深さと鋳型の寸法に関係するので統一は容易ではない。
大手印刷企業の一部では0.918インチ(23.32mm)を採用し、自家鋳造で自社規格の活字寸法で使っている。その他は高さが一定せず0.922~0.927インチの範囲内で使われていたが、活字販売会社は標準的な高さを採用しても、ユーザー各社の寸法に対応しきれない。
当時自家鋳造をしていない中小印刷企業では、活字業者からの買い活字で組版したり、自家鋳造であっても母型がない場合は買い活字で間に合わせていた。
ところが活字の高さの問題で、どこの業者の活字でも使えるというわけにはいかない。たとえば組版を外注する場合、自社の活字の高さと外注の活字の高さが同じでないと印刷できないことになる。つまり互換性がないわけである。そこで書体が良く品質の良い活字販売業者は優位性を保てることになる。
互換性といえば、現代でも似たような現象が起きている。DTPにおけるフォント環境でいえば、同じ書体でもPostScriptフォントがあり、TrueTypeフォントがある。PostScriptフォントのなかにはOCF、CID、ATMフォントなどがある。またTrueTypeフォントにもMacintosh版、Windows版があり互換性はない。
今後新しいフォント形式のOpen Typeが登場してくるという。技術進歩の過程では常に新技術が生まれることは必然的なことと思うが、日本の文字環境に関してはいつの時代でも標準化と互換性の問題はつきまとうものらしい。