印刷業界にとっても動画コンテンツは非常に身近な存在になっている。今後は動画コンテンツから印刷用の静止画像を抽出したり、Web 上で動画と静止画の色合わせを求められたりするようなケースも出てくるだろう。
印刷総合研究会テキスト&グラフィックス部会の月例セミナーでは、「映像制作における色管理とACES を活用したワークフロー」をテーマに取り上げた。富士フイルム 画像技術センター研究マネージャー 内田充洋氏と画像技術センターの大久保彰人氏の講演概要を報告する。
ACES 規格とは
前提として、ここでの映像制作とは映画、CM、放送など業務用動画コンテンツを制作すること全体を指す。制作工程は撮影、編集、VFX(Visual Effects【視覚効果】)合成、グレーディング(カラコレ)、最終処理などの工程に分かれる。この一連の制作工程を一社完結で行うことはまれで、さまざまなプレーヤーがバトンリレーをしながら作品を仕上げていく。
本来は最終仕上りの色を確認(共有)しながら工程を進めていくべきだが、現状は各工程は分断され、最終仕上りとはかけ離れた映像を見て作業を行っているケースも多い。この辺りの事情はCMS が普及する前のかつての印刷業界に近い。当然、映像制作業界においても標準的なカラマネの仕組みが求められ、それがACES(エーセス)という規格となる。
ACES はハリウッド発の規格、正確には米国映画芸術科学アカデミー(AMPAS アンパス)が策定しており、これが最大の特徴とも言える。AMPAS はアカデミー賞の選定で名高いが、科学技術賞という映画に貢献した重要な技術、技術者に贈られる賞もあり、過去には富士フイルムやソニーなど日本の企業、技術者も受賞している。
映像制作においては、まず撮影シーンの全情報を漏らさず入力することが求められる。撮影後のクリエイティブ作業時に充分な調整幅を確保するためと、撮影中に天候の急変などに備えてあらゆる情報を素材に記録しておくためである。
当然、シーンの色を扱う色空間においては、(1)充分な色域を表現できること、(2)充分な輝度レンジを表現できることが求められ、ACESで扱う色空間では、可視光をすべて表現できる色域の大きさを持つとともに表現できる輝度レンジは、16bit half float で反射率にして約0.000006%〜6550400%とほぼ充分な範囲をカバーしている。
前述のようにシーンを撮影するカメラには充分な大きさの撮像レンジが求められる。広大なシーン情報のデータを記録するのでデータ量も膨大になる。記録形式として利用されているのがLOG という形式である。LOG とは対数のことで対数圧縮を利用して広いダイナミックレンジのデータを記録する。より人間の感性に近い感覚で輝度を数値化できるという特性もある。
かつてフィルムをスキャンしてデジタル化していたときには、カラーネガフィルムの特性曲線に合わせてコダックが提唱したCineon という記録形式のLOGカーブが標準的に用いられていたが、フルデジタル時代になって各社のカメラが進化するなか各社のLOGカーブもカメラの特性などに合わせてばらばらに設定されている。このことが標準化が求められる背景の一つとなっている(図1)。
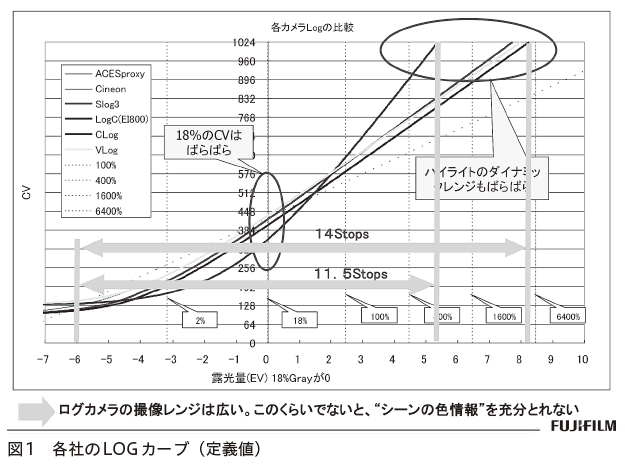
“ 絵作り”の要素もカバーするACES
ICC プロファイルを利用したCMS では測色値(Lab値)を合わせることで、デバイス間の色再現を合わせるものであるが、映像制作においては測色的な色合わせでは不十分である。映画館のスクリーンで色を見たときに、測色値では一致していても人間の知覚としてはオリジナルのシーンの色とは全然違うと感じることが多々あるからである。
その理由は、(1)光源の色順応が高度に考慮されていない。(2)明るさに対する輝度順応が考慮されていない。(3)メディアのフレアの影響が考慮されていないなどがある。これらの点を考慮して補正を行えば、そこそこ色が合ってくる。しかし、まだ不十分であり、もう一つ必要となる要素が“ 好ましい色再現” である。好ましい色再現とは記憶色などがそれに当たる。
例えば肌はより明るく赤みに(黄色人種)、空は、より彩度が高く少々マゼンタを入れる。緑は、より彩度高く、葉っぱは青みに芝生は少し黄みにという感じである。かつて製版スキャナーでは、“ 好ましい(=お客様から校了が取れる)色再現” を行うようセットアップ作業のなかにノウハウが組み込まれていた。測色的な一致だけでは、色再現として不十分というのは非常にうなずける話である。
ACES 規格を用いたCMS では、“ 見えの一致” や“ 好ましい色再現” といった“ 絵作り”の要素までもが包含される。図2 は、それを図解したものである。“ 絵作り”、つまり人間の知覚に忠実な色再現を行う機能がRRT(Reference Rendering Transform) となる。RRT には、映画フイルムの特性と、富士フイルムが培ってきた好ましい色再現の研究成果が大いに含まれている。
色合わせ・絵作りの要素を分かりやすく説明すると以下の3 つ段階を踏むということになる。
レベル1:測色再現(測定値=その瞬間、目に入る色)
レベル2:見えの再現(色順応や輝度順応=その瞬間、脳に入る色)
レベル3:記憶の再現(経過時間変化=時間とともに脳に記憶される色)
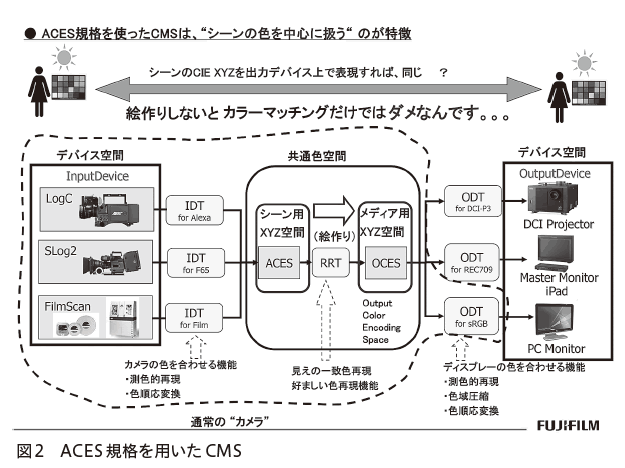 RRT では、このレベル3 に相当する絵作りを実現している。
RRT では、このレベル3 に相当する絵作りを実現している。
図中のIDT(Input Device Transform )とは、入力用のICC プロファイルに当たるようなものであるが、より高度な色順応などが考慮されている。ODT(Output Device Transform)は出力用のICC プロファイルに該当する。
デジタルシネマカメラなどの入力デバイスの色空間からIDT を利用して、まずはシーン用XYZ 空間に相当するACES 空間に変換する。それからRRT により“ 絵作り” を行ってメディア用XYZ 空間に相当するOCES(Output Color Encoding Space)に変換する。そして、ODT を利用して個々の出力デバイスの色空間に変換するという流れとなる共通色空間がACES とOCES と二つあるのは、ACESはシーンの色情報をすべて記録することを想定しており、ACES だけだと色空間が巨大でハンドリングしにくい面があるためだ。そこで、OCES という出力メディア用の色空間が規定されている。
図3 はRRT Ver1 による“ 絵作り” の色変換特性を示したものである。変換の前後で異なるXYZ 値となっているが、その差異により、結果として記憶色や好みの影響を含めて人間が記憶している色と同じように見えることになる。また、RRT により“ 絵作り” をするからといって、どの映像作品も同じテイストになるわけではない。当然、ディレクターのクリエイティビティが問われる。RRTによる変換は料理の下ごしらえのようなもので、そこから真のクリエイティブ作業がスタートすることになる。
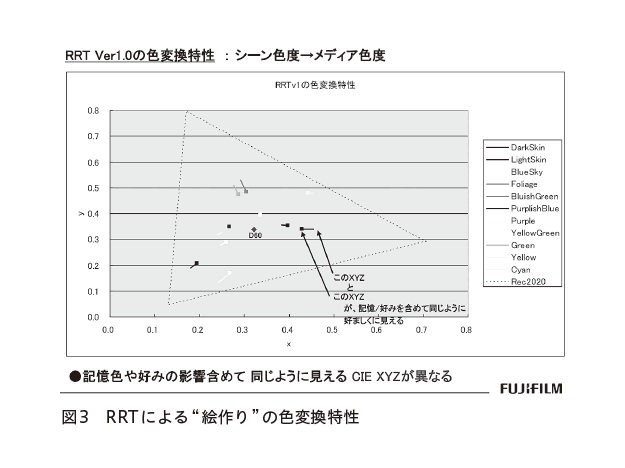
高いCG との親和性-シーンリニアワークフロー
ACES のワークフローはCG 画像との親和性も高い。CG 画像とは、“ シーンの光” を計算したデータの集合ということができる。各画素はシーンの光を数値化したもので、シーンに輝度リニアなCIE XYZ 値に相当するRGB となる。
一方、ACES の色空間も、シーンに輝度リニアなCIE XYZ 値に相当するRGB であるという特徴があるので、ACES 空間でCG 画像と実画像をそのまま合成できる。これがシーンリニアワークフローである。従来、リニアではない実画像のカメラのLOG データとCG 画像の合成には、非常に手間がかかっていたが、これが軽減される。
また、合成結果をプレビューするには、編集作業を行うラボのノウハウが凝縮されたプレビューラット(ルックアップテーブル)が必要で、それは一般に出回るものではなかったが、適切なIDT が入手できれば、AMPAS から提供されるRRT とODT を使うことで汎用的で誰でも使えるプレビュー機能が手に入ることになる。もう一つワークフローの効率化以外に、シーンリニア環境での合成を行うと画質的にも向上することが分かっている。ハイライトのリアリティーの向上や実写とCG の“ なじみ” 具合の向上が見られる。
さらにACES RGB のCG 画像をRRT を用いてRGB変換したところ、人間が記憶している色・階調に近い、よりリアルな画像データが得られたという実験結果もある。
専門用語が多く難解な面もあるが、測色的な色合わせと絵作りの両立というのは、製版・印刷業界が培ってきたノウハウと共通する部分は多い。デジタル化の進展により業界間の垣根はますます低くなっており、今後、印刷業界が動画やCG 画像をハンドリングする機会は増加の一途であろう。その際、技術的なバックボーンを身につける意義は大きいと考えており、テキスト&グラフィックス部会では継続して本テーマは取り上げていきたい。
(『JAGAT info』2016年6月号より/研究調査部 花房 賢)
参考情報:デジタル映像制作ソリューション(富士フイルム)




