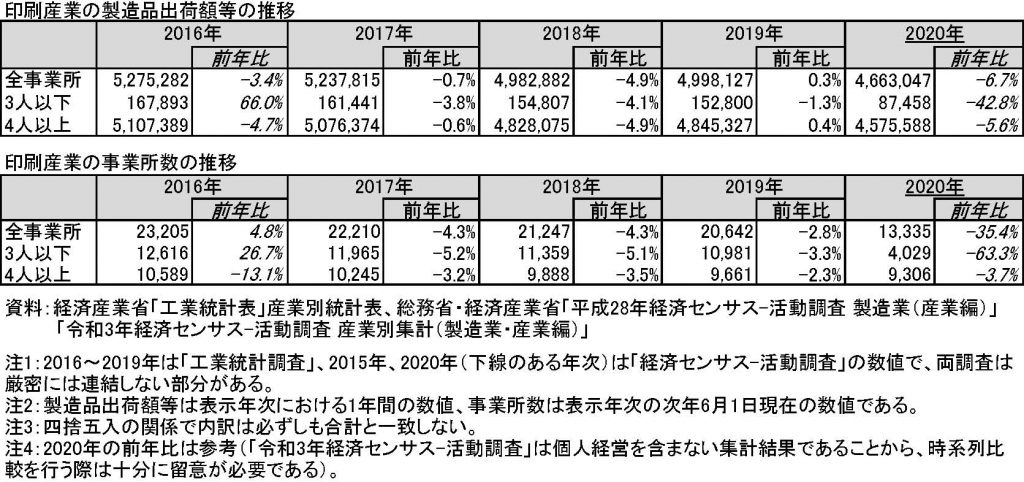2022年の日本の総広告費は、3兆円超えのインターネット広告費が市場を押し上げ、過去最高の7.1兆円となった。(数字で読み解く印刷産業2023その2)
広告市場は15年ぶりの7兆円超え
電通「2022年日本の広告費」が2月24日に発表されました。
「日本の広告費」は、日本国内で1年間に使われた広告費(広告媒体料と広告制作費)を推計したもので、「マスコミ四媒体広告費」「インターネット広告費」「プロモーションメディア広告費」の3つに分類されています。
2022年(1~12月)の総広告費は7兆1021億円(前年比4.4%増)と、コロナ禍で大幅に落ち込んだ2020年から2年連続の増加となりました。新型コロナウイルスの感染再拡大、ウクライナ情勢、物価高騰などの影響はありましたが、社会・経済活動の緩やかな回復に伴い「外食・各種サービス」「交通・レジャー」を中心に広告需要が高まりました。特に、成長が続く「インターネット広告費」によって広告市場全体が拡大し、15年ぶりの7兆円超えとなりました。
「インターネット広告費」は2年連続の2桁成長で3兆円規模に
「マスコミ四媒体広告費」は 2兆3985億円(前年比2.3%減)で、ラジオは2.1%増となりましたが、新聞、雑誌、テレビメディアは減少しました。
「インターネット広告費」(インターネット広告媒体費、インターネット広告制作費、物販系ECプラットフォーム広告費の合算)は3兆912億円(前年比14.3%増)で、初めて3兆円超えとなりました。2019年に2兆円を突破した「インターネット広告費」は、2020年にはコロナ禍でも唯一プラス成長(同5.9%増)を達成し、2021年には2桁成長(同21.4%増)に戻り、「マスコミ四媒体広告費」を初めて超えました。そして、2022年には総広告費に占める構成比は43.5%となり、3兆円規模の市場となりました。
また、マスコミ四媒体の事業者が主体となって提供するインターネット広告媒体費を意味する「マスコミ四媒体由来のデジタル広告費」は、4年連続の2桁成長(前年比14.1%増)で、1211億円となりました。特にテレビ番組の見逃し配信などが急拡大したことで、「テレビメディア関連動画広告費」が350億円(同40.6%増)と前年に続き大きく増加しました。また、radikoやPodcastなどの好調により、「ラジオデジタル」が22億円(同57.1%増)と大きく伸びました。
「プロモーションメディア広告費」は1兆6124億円(同1.7%減)ですが、人流回復に伴い「屋外広告」「交通広告」「折込広告」は前年を上回りました。
「DM」は3381億円(同1.9%減)となったが、前年に続きデータマーケティングを活用したパーソナライズDMやデジタル施策と連動したDMが多く利用されました。
JAGAT刊『印刷白書』では、印刷メディア産業に関連するデータを網羅し、わかりやすい図表にして分析しています。また、限られた誌面で伝え切れないことや、今後の大きな変更点は「数字で読み解く印刷産業」で順次発信しています。
(JAGAT CS部 吉村マチ子)
関連情報
【セミナー】広告と通販、印刷メディアの最新動向
2023年3月28日(火) 14:00-16:50
【コンサルティング型研修】第2期 DM企画制作実践講座
2023年7月11日(火)~10月5日(木)