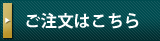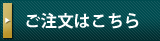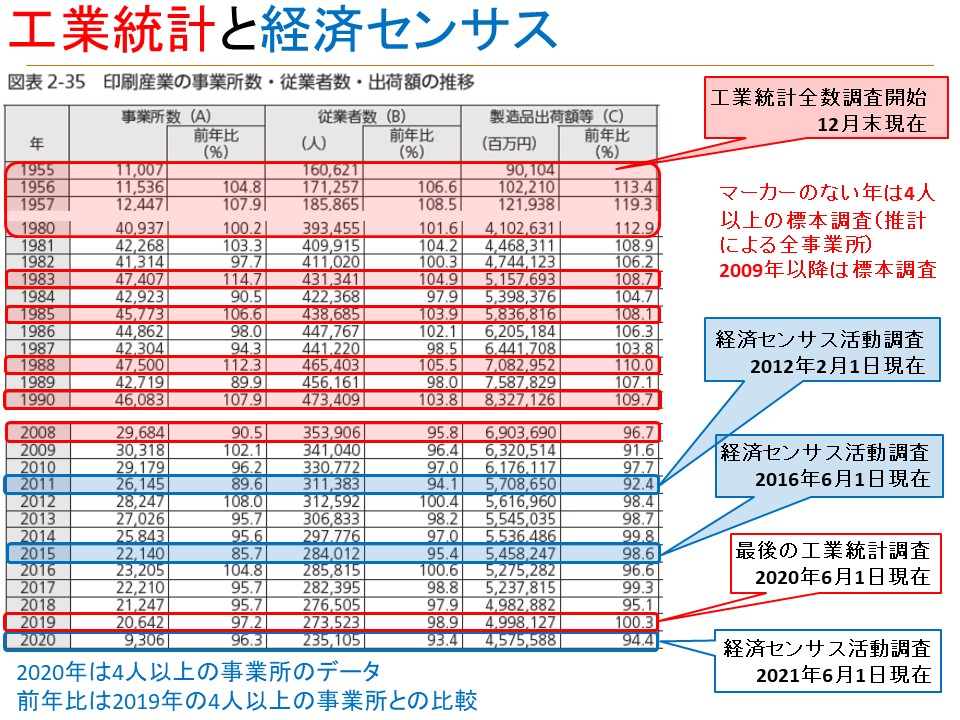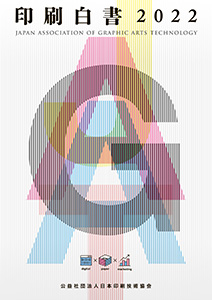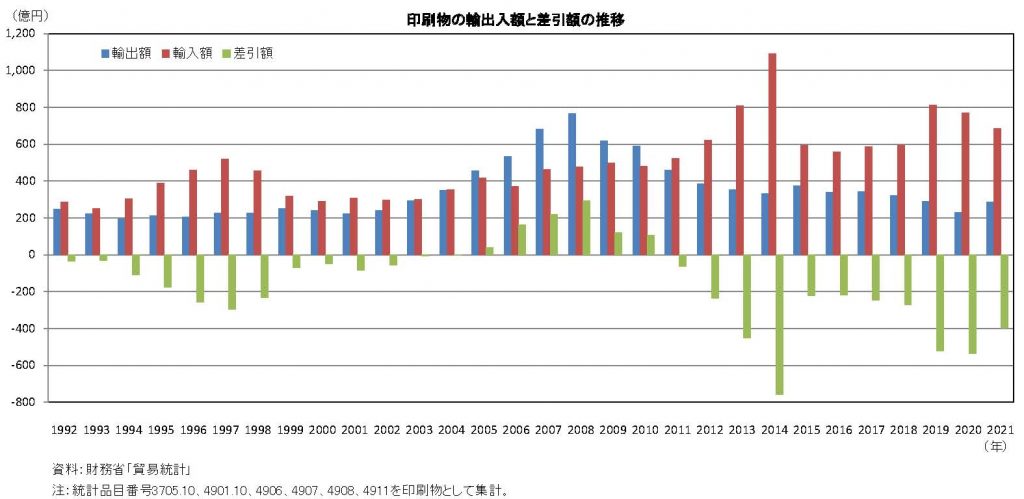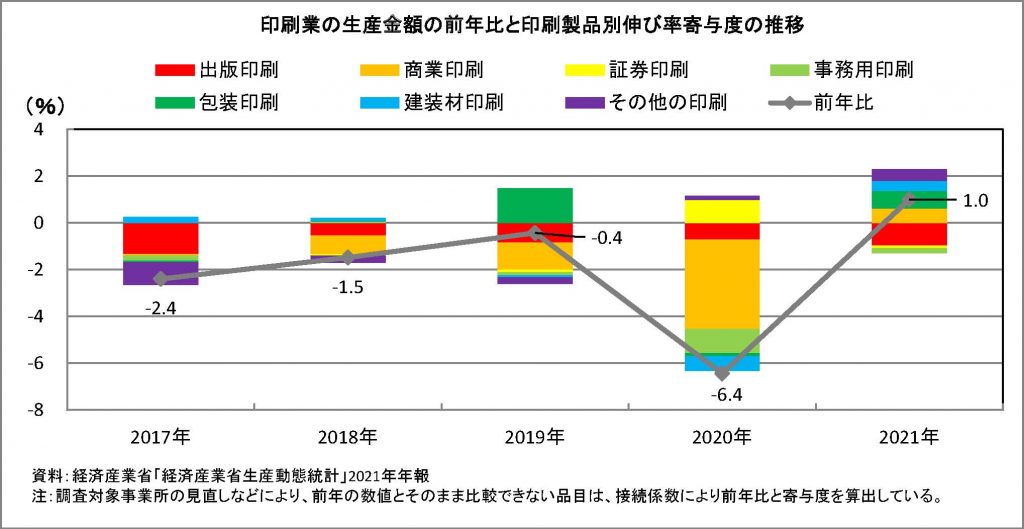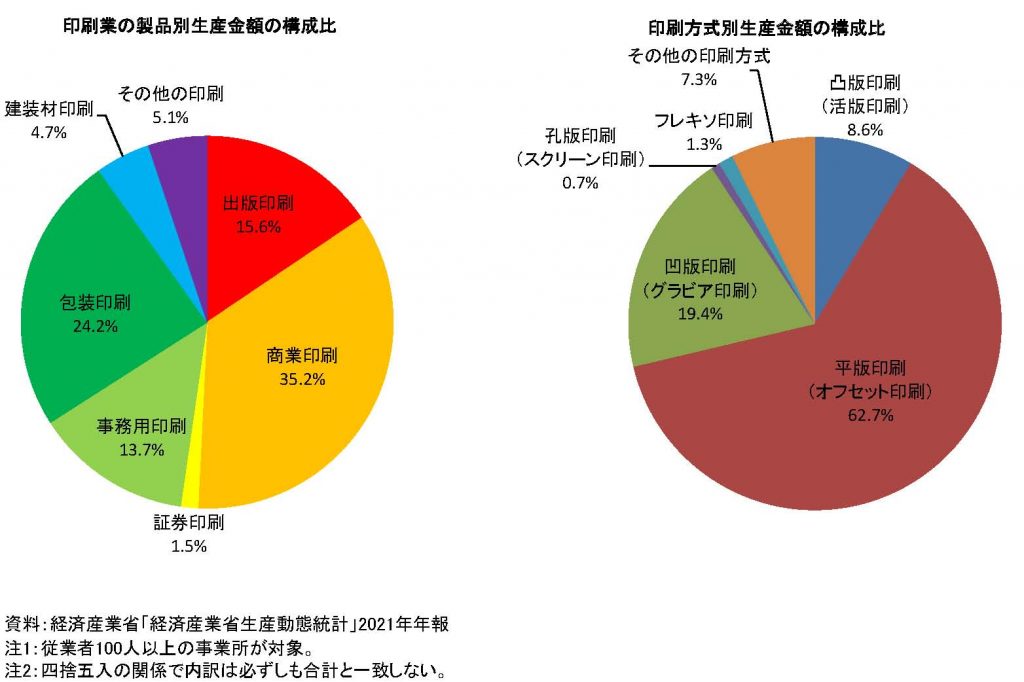2021年度の法人企業統計調査で全産業の経常利益は過去最高となり、印刷産業も大きな伸びを達成した。上場企業の2022年3月期決算は3社に1社が最高益となり、上場印刷企業33社のうち22社が増益となった。(数字で読み解く印刷産業2022その6)
2021年度の経常利益は過去最高を更新~法人企業統計
9月1日発表の財務省「法人企業統計調査」によると、2021年度の全産業(金融業、保険業を除く)の経常利益は、前年度比33.5%増の83兆9247億円で、3期ぶりに増益に転じ、比較可能な1960年度以降で過去最高を更新しました。
製造業は同52.1%増の33兆1940億円、半導体関連の需要が増えた「情報通信機械」や「化学」が増益に寄与しました。非製造業は同23.7%増の50兆7307億円、原油価格の上昇で利益が拡大した「卸売業、小売業」や、前年度に大きく落ち込んだ反動で「サービス業」が好調でした。
売上高は同6.3%増の1447兆8878億円と、4期ぶりの増収でした。設備投資額(ソフトウエアを含む)も同9.2%増の45兆6613億円となり、3期ぶりにプラスに転じました。
印刷・同関連業について見てみると、売上高は同3.2%減の7兆6652億円で、2期連続の減少だが、経常利益は同49.6%増の2779億円で4期ぶりに増益に転じました。設備投資額(ソフトウエアを含む)は同16.8%減の1660億円で、6期連続のマイナスで減少幅は拡大しています。
上場企業は3社に1社が最高益、上場印刷企業22社が増益を達成
2022年3月期決算の上場企業約1890社(金融など除く)のうち、最高益となった企業の比率は30%と約30年ぶりの高水準になりました。日本経済新聞が5月13日までに業績を発表した上場企業を対象に集計したところ、7割の企業の純利益が前期より増え、最高益となった企業の割合も1991年3月期以来の多さでした。
JAGAT『印刷白書』では、社名もしくは特色などに「印刷」とある企業33社を、上場印刷企業としています。前回までは34社で分析してきましたが、トッパン・フォームズが凸版印刷の完全子会社化により2022年2月25日付けで上場廃止となったことから、現在編集中の『印刷白書2022』では33社となっています。各社の業績は決算短信と有価証券報告書で見ていますが、提出時期の関係で2021年6月期決算から2022年5月期決算までを2021年度としています。
ちなみに、2022年3月期から「収益認識に関する会計基準」が、上場企業や大会社に適用されるようになりました。収益認識基準の導入は、既にIFRS(国際財務報告基準)を適用している企業にとって影響はありませんが、日本基準の企業にとっては売上高が減少して見えるほどの大きな影響があります。
2022年8月現在IFRSを適用している上場企業は251社、印刷会社ではNISSHAとプロネクサスの2社が適用しています。
上場印刷企業33社のうち、IFRS適用の2社を除き、2022年3月期~5月期が決算の19社が、収益認識基準を適用していて、そのうち12社が売上高が適用前と比べて減少したとしています。
33社の2021年度売上高合計は3.8兆円(前期比3.4%増)ですが、適用前の数字ならもっと大幅な増収だったことになります。
コロナ禍が続く中で、個人消費や企業活動の停滞、紙メディアの需要減少、原材料価格の高騰など、印刷業界にとって厳しい経営環境にありますが、増収21社、増益22社となりました。
『印刷白書2022』は10月下旬発行を予定しています。上場印刷企業33社の分析では、事業展開の特色と売上高構成比、個別業績による規模・収益性・生産性・安全性・成長性、連結業績による設備投資総額・研究開発費、キャッシュフローバランスなどを比較しています。
限られた誌面で伝え切れないことや、今後の大きな変更点は点は「数字で読み解く印刷産業」で順次発信していきます。ご意見、ご要望などもぜひお寄せください。
(JAGAT CS部 吉村マチ子)