「協会情報」カテゴリーアーカイブ
1/26 印刷とメディアの動向と展望2021-2022
トピック技術セミナー2021 オンライン
トピック技術セミナー2021 オンライン
確実に成果につながる広告の「型」を学び、顧客満足を得るDMを制作する
11月25日に開催したオンラインJAGAT大会2021では、マーケティングの専門家ロン・ジェイコブス氏が基調講演を行い、アメリカにおける最新のダイレクトメールの活用状況や変化について解説した。アフターコロナを見据え進化するDMは、ニューノーマル時代に印刷ビジネスに新たな価値をもたらす可能性が大きい、と期待させる内容であった。 続きを読む
更新合格者への認証カード発送に関するご報告
2021年9月実施更新試験合格者のみなさま
11月15日に発送しました認証カードの誤封入につきまして、ご迷惑をおかけしておりますことをあらためてお詫び申し上げます。
現在の状況をご案内いたします。
【誤封入分をお届けしてしまった方へ返送のお願い】
誤封入分をお届けしてしまった皆様には、11月30日に着払い返送用レターパックをお送りしました。
御手数ではございますが、11月15日ごろ届きました【DTPエキスパート認証カード在中】と記載のある封筒をそのまま返送用レターパックに入れ、ポスト投函いただけますようお願い申し上げます。
【正しい認証カードのお届け】
現在、全合格者の認証カードを再作成しております。
12月21日頃発送の見込みで進行しておりますので、到着まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
(当初のご案内より遅れておりますことを重ねてお詫び申し上げます。)
到着までに資格証明をご入用の場合は、証明書類を即日発行いたしますので、
お手数ですがJAGAT資格制度事務局までその旨ご一報くださいますようお願いします。
JAGAT資格制度事務局
e-mail: expert@jagat.or.jp
tel: 03-3384-3115
3/24 JAGATトピック技術セミナー2022-2023
【マスター郡司のキーワード解説2021】レストアサービス(G-SHOCK)
印刷会社へ入社した理由の15%がマーケティング!~若手の意欲に教育と実践機会を~
印刷会社がマーケティングを強化するには人材が重要である。実務経験が豊富な中途人材を採用するのも一つではあるが、マーケティングの仕事を希望し、印刷会社を志望する若手人材も増えている。
続きを読む
JAGAT大会2021とpage2022でマーケティング理論を実践へ
今年度の「JAGAT大会2021」は2021年11月25日にオンラインで開催する。
より多くの印刷およびメディア関連事業に携わる皆さまに弊会コンテンツを提供するべく、広く一般の方々にもご参加いただけるオンラインイベントとした。JAGAT会員企業様及び印刷総合研究会会員様は無料で聴講可能です。 https://www.jagat.or.jp/jagat_convention2021
先進事例を自社に置き換えて考える
JAGAT大会2021オンラインでは「page2017」の基調講演に登壇したロン・ジェイコブス氏の「afterコロナを見据えた印刷業界」をテーマにした基調講演と、その講演内容についてのディスカッションをするという構成である。今回特にディスカッションに重きを置くべく、講演部分を2つに分け、それぞれに解説とディスカッションを加えて2部構成としている。アメリカの事例を聞いてふーん、で終わるのではなく、解説とディスカッションを経て、自社に置き換えて考えるきっかけにしていただきたいという想いから構成を変更した。
そして考えて終わりではなく、行動に繋げていただくべく、page2022(2022年2月2日~4日@サンシャインシティ)でも様々な企画を用意した。まず展示会場に「デジタルマーケティングサービスゾーン(仮称)」を設置する。ここではデジタルマーケティング関連サービスを展開する企業を広く集めるだけでなく、マーケティングを市場の創出、顧客の創造と捉えて、幅広い業種から様々な製品、サービスを集める予定だ。
印刷関連企業の新たなチャレンジをサポート
また今回のpage2022においては、貴社の製品・サービスなどの紹介動画コンテンツを配信しその動画の視聴者情報(リスト)を得ることが出来る動画配信プランもご用意している。このプランに、テーブルブース出展を組み合わせたセットプランを設定した。テーブルブースは、通常の出展小間とは異なり、カウンター形式のミニブースであるが、ブース説明員の人員を最小限に抑えることができる。リーズナブルな出展料金と合わせて、新規の出展企業にとっては最適な出展プランである。
JAGAT大会で学びpageで行動に
マーケティングは概念だけを学んでもあまり効果は無く、実務での試行錯誤が必須である。敏腕マーケターであればあるほどトライアンドエラー、そして「テストマーケティング」を繰り返し、最適解を見つけ出す。これまでのJAGAT大会は企業トップにご参加いただくことが多かったが、今回は無料でオンライン視聴が可能となるので、ぜひ社歴の若い方にもご視聴を促していただきたい。そして新規事業開発のようなチャレンジのきっかけと、それを実行に移すテストマーケティングの場を与えていただきたいと思う。コロナ化を乗り越えつつある今だからこそ、若い力の新たな発想や行動力に期待しても良いのではないか。
(CS部 堀雄亮)






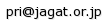 )またはTEL(03-3384-3113)にてお問合せください。
)またはTEL(03-3384-3113)にてお問合せください。