JAGAT info 1月号では取引先の業務に深く関わり、BPOとして仕事の一部を請け負うことで成長を続ける研文社の事例を紹介した。 今回はその一部を抜粋して紹介する。
BPO を得意とする印刷会社
研文社は1946 年に、現社長である網野勝彦氏の祖父が大阪市で設立した。まだ活版印刷が主流だった時代に日本で2 番目にオフセット印刷機を導入(1952 年)した会社であり、新しい技術を積極的に取り入れてきた歴史がある。大きな転機となったのが、得意先の銀行が軸足を東京へと移すのに合わせて、東京進出を勧められたことである。文京区にあった印刷会社と現在でいうところのM&A を行い、1960 年に東京研文社というグループ会社を立ち上げることになった。
研文社の特徴の一つが、顧客の仕事の一部を改善や効率化を含めて請け負うBPO(Business Process Outsourcing)が成果を結んでいる点である。元々は印刷だけを請け負っていたが、徐々にテキストの作成や配送業務など周辺の業務を含めて受注するようになっていった。同社では、BPOのために人材の育成や配送センターの設立などの投資を行っている。
このBPO は、印刷業務だけではなく関連する業務も合わせて一括受注している。そのため、印刷需要が減少する時代にあっても、売り上げを伸ばすことが可能である。また、業務に深く関わり、他の印刷会社では提供が難しいサービスを行っていることから、クライアント側も別の印刷会社に業務を移管することは簡単にはできなくなる。結果的に価格競争を免れることから、印刷会社が生き残るための一つの戦略と考えられよう。
研文社がデジタル印刷分野に進出したのは、網野勝彦氏の父である現会長・網野博氏がスクリーン社のロールタイプのインクジェット機、Truepress Jet520 を、2012 年の尼崎工場新設時に導入したのが始まりだった。
もともとはフォーム印刷用として想定したものだったが、網野勝彦氏の代になり、尼崎への工場集約を機にデジタル印刷を軌道に乗せるため編み出したのが、デジタル印刷ならではのサービスを提供・販売していくことだった。その最たるものが、現在もデジタル印刷の主力製品となっている福祉用具のカタログである。
福祉用具は、自治体によって補助率などの制度が異なるため、価格が自治体ごとに変わってくる。個別かつ細かな仕様変更が必要であり、小ロット・バリアブルの極みともいえる印刷業務である。これら福祉用具カタログの業務の仕組みやZ 折の機体構成については、過去にも本誌2013 年8 月号や2017 年11 月号で詳細に紹介している。
この福祉用具カタログを中心に、尼崎工場では利益の半分をデジタル印刷が生み出すようになった。アナログ印刷よりも少ない業務量で同規模の利益を稼ぎ出せており、デジタル印刷の特徴に合致したビジネスモデルのケースといえる。
東京の本社工場をデジタルに特化
尼崎工場が軌道に乗り、デジタル印刷のビジネスモデルが分かったことで、現在改革に着手しているのが新宿区の本社工場である。建物の地上部分には本社機能や営業部門などがあり、地下1 階と地下2 階が工場となっている。
地下2 階部分では、主にメインクライアントの一つである銀行の印刷部門から移管された業務を行っている。地上2階部分にはコールセンターを設置、全国の銀行支店や担当部署から受注が随時集まる仕組みができている。
地下2 階の設備は、リコーのデジタル印刷機、RICOHPro C7210Sが2 台とRICOH Pro 8320Sが1 台置かれており、その他に製本機や折機、断裁機が一式そろっている。
そして、本社地下1 階にはオフセット印刷機2 台を売却して、同じ場所にImpremia IS29とJETvarnish 3Dを導入した。Impremia IS29 は1200dpi の解像度を持ち、585mm × 750mm までの大きさの紙に印刷できる。幅広い用紙適性と、パッケージ印刷にも対応可能な紙厚適性を持つ。
これに加えて、JETvarnish 3D で箔やニスを装飾することができる。研文社では現在、8 種類の箔を用意している。価格は高くなるが、他社との差別化が可能な、高級感のある印刷物の制作が可能となる。実際に目で見て触ってみれば、その差は歴然であり、提案営業をしていく糸口の一つとなっている。
また、地下1 階では、デジタル印刷の特性を生かし、顧客が立ち合って実際の刷り上がりを見ながらデータを修正し、再度その場で印刷することもできるようにした。大きな修正の場合、オフセット印刷では、また後日の確認ということになりがちだが、デジタル印刷であれば、データを修正した後は印刷・箔押しまで含めてもその場で修正された印刷物が出来上がる。刷り上った印刷物とサンプルをお互いに見比べながら、イメージを共有していく場となる予定である。
アライアンスでIT を強化
研文社は、(株)グーフと2020 年8 月に資本業務提携を締結した。グーフはパーソナライズされた印刷物を最短24 時間で発送可能な印刷プラットフォーム、Print of Things®を展開しており、その生産部分や付帯サービスを同社が担う格好だ。こちらでもImpremiaIS29、JETvarnishの活用が検討されている。
研文社では、グーフのようなIT を得意とする企業とアライアンスを結ぶことで最先端のサービスを提供している。今回はその連携を一歩先へ進めた格好であり、同社としてもこれまで培ってきた自社の技術、ノウハウが生きる業務提携となっている。もちろん、個人情報を取り扱うためセキュリティーなどには注意が必要だが、古くから銀行と仕事をしてきた同社にとっては、むしろ得意分野だろう。また、配送センターを複数運用してきた実績もあることから、印刷から発送までを迅速に行うことも可能だ。
つまり、ここにImpremia IS29 とJETvarnish 3Dを組み合わせていくのが、研文社の狙いである。Printof Things® では定型のハガキ類を送ることで成果を上げているが、絞り込みの条件によっては、より確度の高い見込み客を抽出することも可能である。送付対象が多い場合は通常のDM、少ない場合は高付加価値印刷のDM といったように、幅広い選択肢が作れるようになれば、サービス強化につながる。このアライアンスでは、IT と広色域+ 加飾の組み合わせで、印刷の新しい可能性を広げようとしている。
販促企画のBPOで案件単価を上げる
また、Impremia IS29の活用については、他社との協業だけではなく、もともと強みとしてきた営業を武器に、自分たちからも仕掛けていくつもりである。そこでもメインの商材の一つとして考えているのが、高級DM である。
研文社の関連会社には、事業開発部クリエイティブ室を移管した(株)ケンズがあり、広告・販促物の制作やプロモーション戦略の立案、プロデュースなどを行っている。Impremia IS29とJETvarnish 3Dで印刷するプロモーションメディアは、企画段階からケンズとともに起案している。企画から編集、制作、印刷までトータルで売り込むことで、一つのBPO として案件の単価を上げていく考えだ。
まだ手探りの段階であるが、大ロットの印刷物が減少していくなかで、印刷物+ αの価値を提案していくことは、今後ますます重要となる。原価から値付けを決めるのではなく、広告効果や付加価値をアピールし、利益率の高い商品に育てていく戦略だ。
研文社は、印刷業務を核としつつ、IT の活用やBPOで業務領域を広げ、売り上げを伸ばしてきた。高単価・高付加価値のデジタル印刷は研文社にとっても新たな挑戦となるが、新しいアライアンスや販促企画などを含めた営業活動で利益率の高い事業を開拓しようとしている。
(研究調査部 松永 寛和)





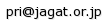 )またはTEL(03-3384-3113)にて、お問合せください。
)またはTEL(03-3384-3113)にて、お問合せください。