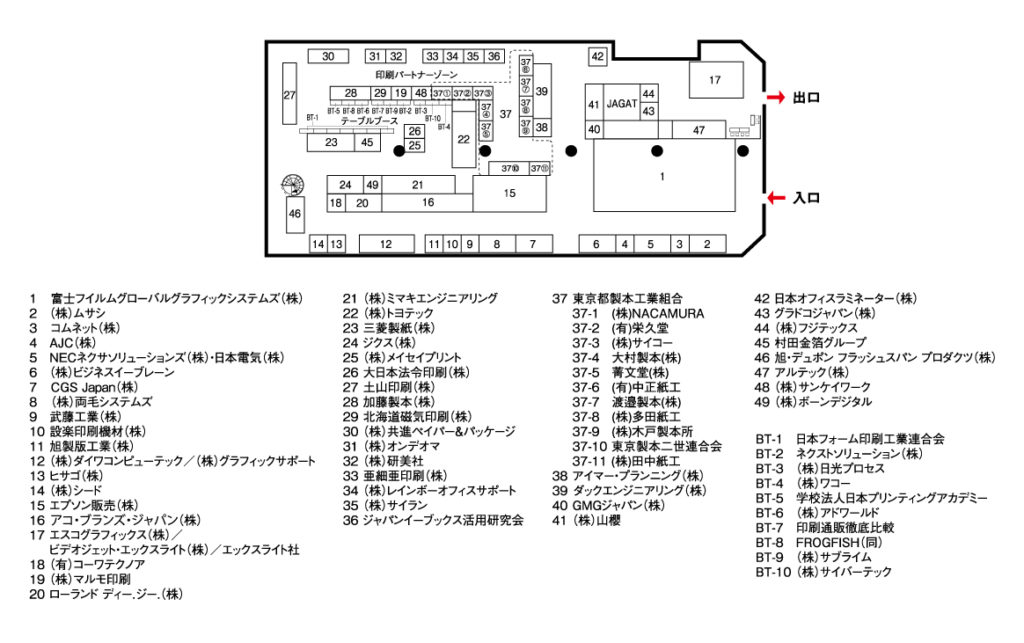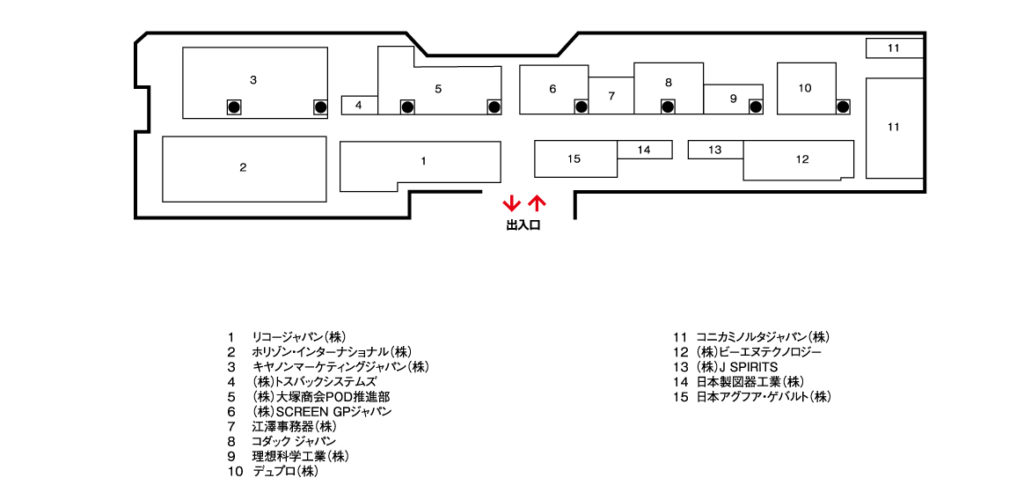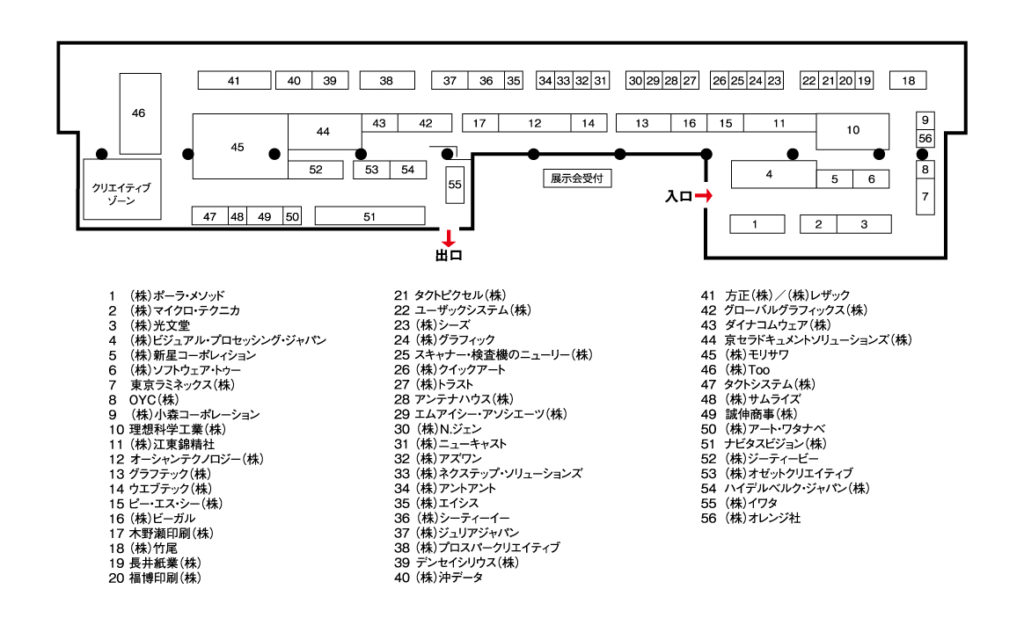経営者が自ら取り組む商品開発とデザインへの取り組み
印刷業を取り巻くビジネス環境では、デザインの重度が増している。販売促進ツールをはじめとするBtoBや生活者を豊かにするBtoCの商品開発を手掛ける印刷、紙加工業の事例も増えてきている。商品開発に欠かせないのが、アイデアとそれを形にするデザインだ。
page2020セミナー「アイデアを形にする紙加工の製品開発」では、紙加工製品の商品開発に取り組む2社に実践でのプロセスとブランド展開について解説する。
加藤製本株式会社では、ブランド「クルーシャル」を立ち上げている。クルーシャルは、文具、朱印帳などの紙加工商品を開発し、提供する会社だ。プロダクトデザイナー、グラフィックデザイナー、CADエンジニア、一級技能士の資格を持つ社員によりものづくりに取り組む。社員がアイデアを出すこととデザイナーを採用や育成することに力を入れている。同時に、大手文具量販店や文具店、女子博、販促アイデアグランプリ展など業界の枠を超えた販路開拓にも力を入れている。マーケティングとアイデアとそれを形にするデザインの相乗効果で成果を上げている。紙加工技術、レーザーダイカットシステムを活かした微細な細工の朱印帳やマカロン(付箋)などは記事や話題として取り上げられことも多い。
福永紙工株式会社では、この2020年1月29日までの期間で昨年11月にオープンした渋谷スクランブルスクエア10Fの東急ハンズが運営する「208HANDS」で販売会を実施している。ブランディングへの取り組みだ。クリエイターと共にこの12年間でつくりあげた紙製品の22日間限定販売会だ。同社は、印刷から加工までのパッケージの印刷加工会社として1963年に創設された。転機は、アパレル商社勤務経験とノウハウを持つ現在の山田社長を中心とした2006年の「かみの工作所」プロジェクトスタートだった。多くのクリエイターと恊働して工場の技術を活かしたオリジナル製品の企画、開発、製造、販売への挑戦をはじめたことだ。第一線のクリエイターとの人脈も広い。他にも1/100スケールの模型ブランド「テラダモケイ」の製造販売など、新たな紙の価値を模索する取り組みを様々な形で行っている。海外の美術館でも取り上げられるような「空気の器」「MABATAKI NOTE」などの製品は、ブランド価値をさらに高めている。
デザインがビジネスチャンスへ
印刷会社がマーケティングや製品においてデザイン能力を重要視しているように顧客側の企業もデザインノウハウを重要視している。印刷業でもビジネスチャンスとして捉えるべきだ。また、消費者ニーズが複雑化し課題がわかりにくい市場においては、デザイン的な発想やデザイナーが重要になってきている。商品開発の決め手はアイデアだ。モノや情報が溢れた時代では、ユーザーの想定を超えた製品やサービスが必要なる。〝今までにない”紙製品を創り〟で販路開拓し、ブランディングを展開するポイントを紹介する。また、アイデアやデザイン的な発想は、簡単に出せるものではない。アイデアを生み出すために取り組むべきことは何か、そのためのポイントも解説する。
CS部 古谷芸文
関連情報 page2020セミナーhttps://page.jagat.or.jp/sessionList/seminar.html
【S9】アイデアを形にする紙加工の製品開発