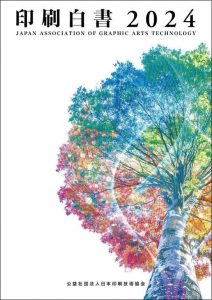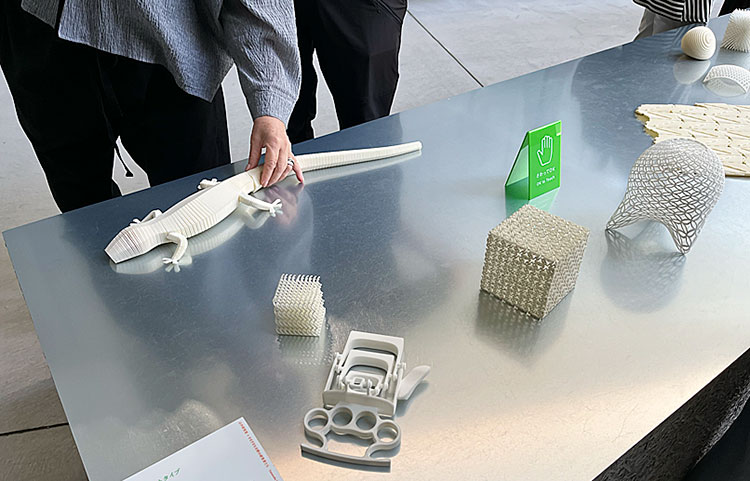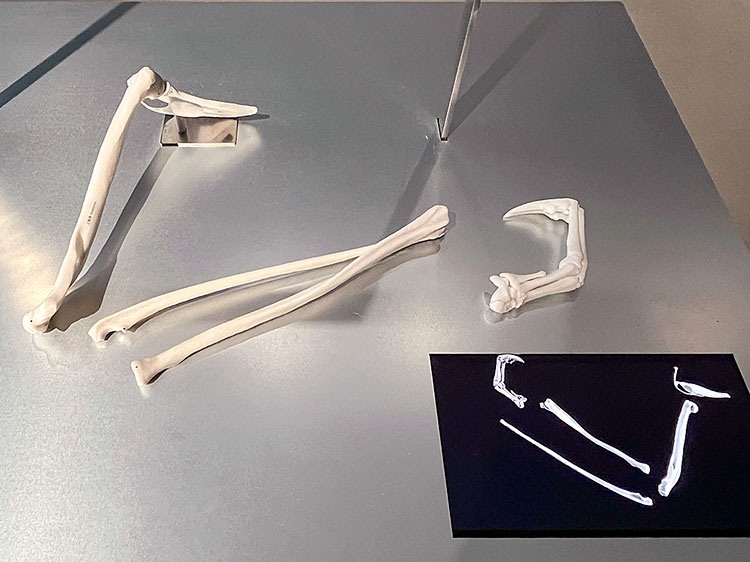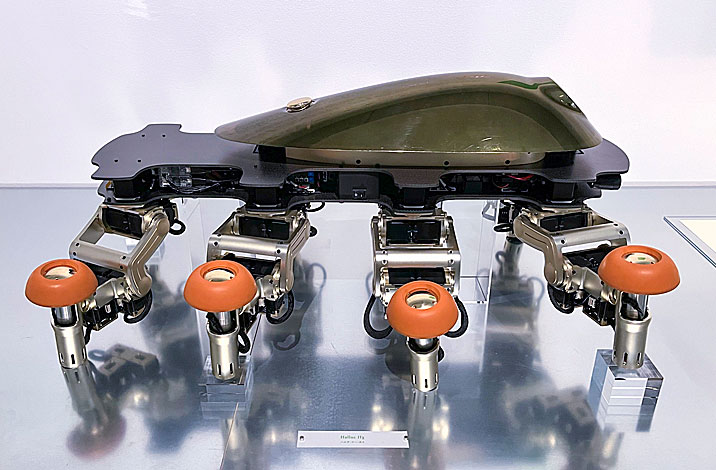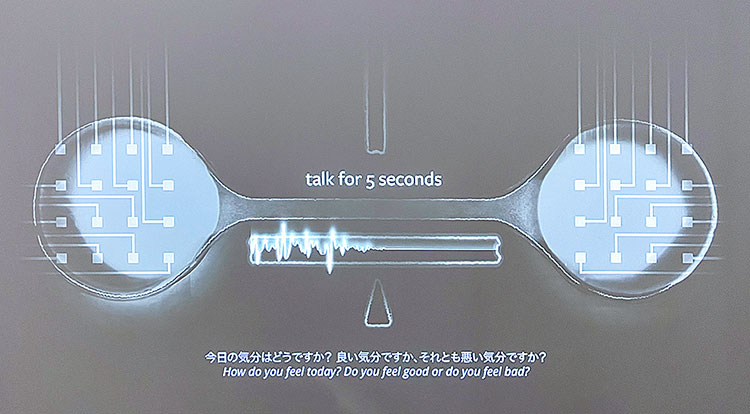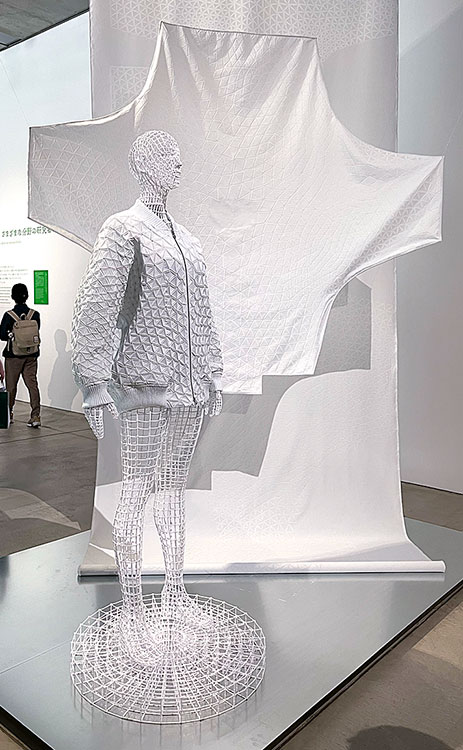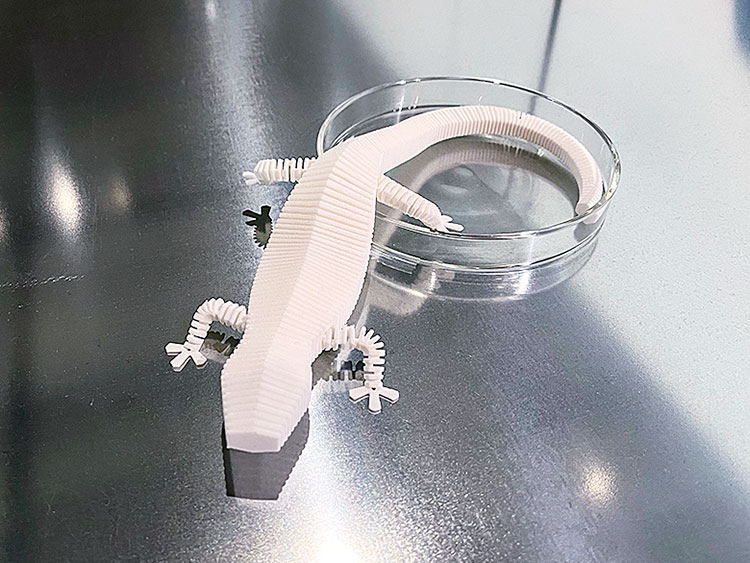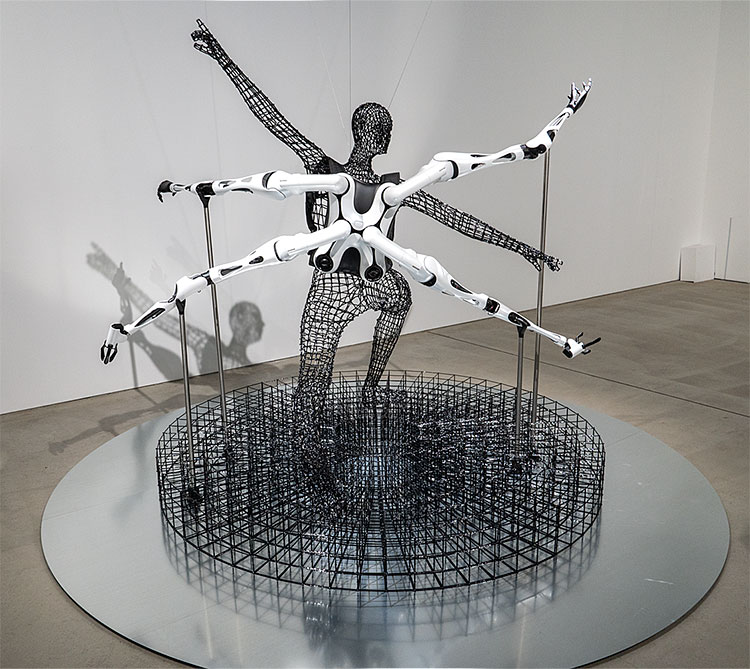デザイン専門の展示施設「21_21 DESIGN SIGHT」で2024年9月27日〜2025年2月16日まで開催された企画展「ゴミうんち展」の概要と作品の一部を紹介する。 続きを読む
「デザイン」タグアーカイブ
日本の季節と色と形(4)
会員誌『JAGAT info』の表紙のデザインについて紹介する。
会員誌『JAGAT info』の表紙のデザインは、印刷文化を語る上で欠かせない、色と形をテーマにしており、現在は「日本の形シリーズ」として、本誌の発行時期の歳時や風物をモチーフを主体にして、季節感と日本情緒が感じられるようなものとしている。
参考:『JAGAT info』バックナンバー →
では最近のバックナンバーから、表紙に描かれたモチーフについて解説し、制作手法を紹介しよう。
2024年10月号 「キノコ」
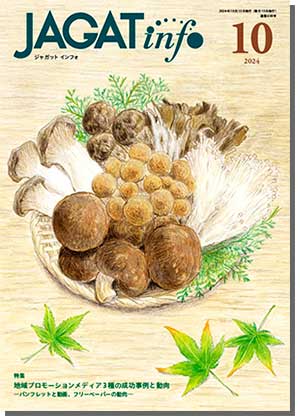
そろそろ肌寒くなる時季であることから、鍋物や煮物などの温かい料理に活躍する食材であるキノコをテーマにした。
料理にキノコ類を入れるとうま味が増すし、シンプルに、バター焼きやホイル蒸しにしてしょうゆを垂らしてもおいしい。制作中は、我が家の食卓でもキノコを入れた炒め物や自家製の「なめたけ」の出番が増えた。
表紙に描いたのは椎茸・エリンギ・松茸・舞茸・ブナシメジ・エノキタケだが、他にも多くの種類がある。品種によって色も形もさまざまであり、それぞれの特徴を出すのは難しくもあり楽しくもあった。
制作に当たっては、色鉛筆で手描きした後、スキャンし、ptohoshopで色調を調整した。
なお、キノコで思い出すのは、2024年12月19日に逝去された絵本作家・いわむらかずお氏による『14ひきのあさごはん』。どんぐりパンときのこのスープを囲んだ朝食風景が微笑ましかった。
2024年11月号 「サザンカ」
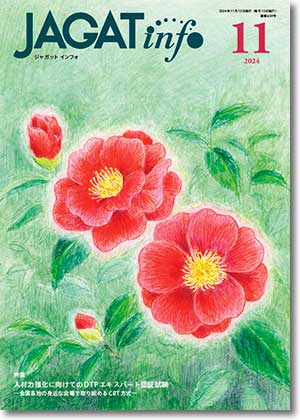
サザンカとツバキは、どちらもツバキ科ツバキ属に属していることから、区別がつきにくい。
しかしよく観察すると明らかな違いがある。
例えばツバキの花弁は付け根が合着して筒状になった、いわゆる合弁花であるが、サザンカの花弁は一枚ずつ分かれている。そのため花が終わるとツバキは咲いた形のままポロリと落ち、サザンカは花弁が1枚ずつ散る。
雄しべの形も、ツバキの場合、花の中心部の花糸(雄蕊の中で、先端の花粉嚢を支える部分)同士が接着して筒形になっているのに対し、サザンカの花糸は一本一本が離れている。
また葉を見てみると、ツバキの場合、先が尖った卵型でつやと厚みがある。一方サザンカの葉はツバキより小ぶりで、表面に艶はなく、葉の縁がギザギザしている。
制作に当たっては、11月号と同様、色鉛筆で手描きした後、スキャンし、ptohoshopで色調を調整した。
2024年12月号 「白蛇」
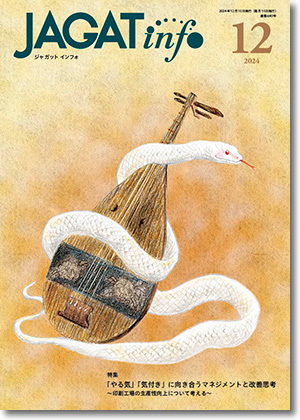
2025年の干支にちなみ白蛇をテーマとした。
白蛇はアオダイショウなどが色素異常で白化した個体(アルビノ)のことを指す。山口県岩国市には古くから白蛇が多数生息し、白化が子孫に受け継がれている希少な例であることから「岩国のシロヘビ」として国の天然記念物に指定されている。
日本の絵画ではたびたび、琵琶に絡み付いた白蛇が描かれている。その由来は、白蛇が弁財天の使いであり、弁財天が持っている楽器が琵琶であることによるとされている。
筆者は爬虫類が苦手ではある。しかし白蛇の顔をよく見ると、目は丸くて赤く、口元は笑っているようにも見えなくもない。そのため、描き上げた白蛇の表情は可愛げのあるものとなった。
制作に当たっては、白蛇と琵琶を色鉛筆で描いてスキャンし、和紙のテクスチャーに色を乗せた画像を背景に合成した。
表紙絵を担当していると、日本文化の歴史や他国との関係などを知ることができ、対象となるものを観察することで思わぬ発見もある。今後もさまざまな題材を通じて、日本の風物の魅力を伝えていきたい。多忙な日々を送る読者の方々が、本を手に取る一瞬にホッと一息ついていただければ幸いである。
(『JAGAT info』制作担当 石島 暁子)
関連ページ
印刷会社とキャラクタービジネスの関係は
印刷業界は大きな転換期を迎えている。デジタル化の波に押され、従来の印刷ビジネスモデルだけでは生き残りが難しくなっている。そんな中、新たな可能性を秘めた市場として注目を集めているのが、キャラクターグッズ市場だ。
続きを読む
デジタル時代のDTPプロフェッショナルになるために
デジタル時代の到来により、印刷業界は大きな転換期を迎えている。かつては紙媒体が主流であったが、今や情報伝達の手段は多様化し、デジタルコンテンツの需要が急増している。この変化に伴い、DTPオペレーターやデザイナーには新たなスキルセットが求められるようになった。
続きを読む
デザイン制作における生成AIの活用とは
デザイン制作における生成AIの活用は、クリエイティブ業界に革命をもたらしつつある。従来のデザインプロセスを根本から変え、効率性と創造性の両面で大きな進歩を遂げている。
続きを読む
JAGAT主催の事業をうまく活用する
−『JAGAT info』11月号のご案内−
JAGATではX(旧:Twitter)アカウントも運用している(@jagat_labs)。先日、『DTPエキスパート・マイスターBOOK』の新刊告知をアップしたところ、過去に例のないインプレッション数となった。 続きを読む
印刷白書2024
解説
印刷産業のこれからを知るために必携の白書『印刷白書2024』
あらゆる産業を顧客とする印刷産業は、さまざまな産業と密接に関わりを持っています。「印刷白書」では、印刷産業の現状分析から印刷ビジネスの今後まで幅広く取り上げています。
印刷・同関連業界だけでなく広く産業界全体に役立つ年鑑とするために、社会、技術、産業全体、周辺産業というさまざまな観点から、ビジョンを描き込み、今後の印刷メディア産業の方向性を探りました。
印刷業界で唯一の白書として1993年以来毎年発行してきましたが、2024年版ではdrupa、サステナビリティ、事業承継などの項目を追加しました。
印刷関連ならびに情報・メディア産業の経営者、経営企画・戦略、新規事業、営業・マーケティングの方、調査、研究に携わる方、産業・企業支援に携わる方、大学図書館・研究室・公共図書館などの蔵書として、幅広い用途にご利用いただけます。
「第1章 Keynote」では印刷会社の「共奏ビジネス」をテーマに、印刷ビジネスの課題解決に取り組んでいます。「第2章 印刷産業の動向」では印刷産業の現状と課題を俯瞰的に捉え、「第3章 印刷トレンド」では技術課題を整理しました。「第4章 関連産業の動向」ではクライアント産業の動向を探りました。「第5章 印刷産業の経営課題」ではサステナビリティから人材まで印刷産業が取り組むべき課題を整理しました。
印刷メディア産業に関連するデータを網羅し、UD書体を使った見やすくわかりやすい図版を多数掲載し、他誌には見られないオリジナルの図版も充実させました。
CONTENTS
第1章 Keynote 「共奏」ビジネス
印刷ビジネスは「創注」から「連携」、そして「共奏」へ
第2章 印刷産業の動向
[産業構造]多くの可能性を秘めている印刷テクノロジーの対応力
[産業連関表]あらゆる産業に提供される印刷製品・関連サービス
[市場動向]共創による価値創出へのビジネスモデル革新 インフレ時代の利益成長に向けて
[上場企業]サステナビリティの実現と企業価値向上を目指す上場印刷企業
*関連資料 産業構造/産業分類・商品分類/規模(1)/規模(2)/規模(3)/産出事業所数(上位品目)/産出事業所数・出荷額/調達先と販売先/産業全体への影響力と感応度/最終需要と生産誘発/印刷物の輸出入額と差引額/印刷製品別輸出入額/印刷物の地域別輸出入額/印刷物の輸出入相手国/経営動向/上場企業/生産金額(製品別)/生産金額(印刷方式別)/売上高前期比・景況DI/設備投資・研究開発/生産能力/紙・プラスチック/印刷インキ/M&A
第3章 印刷トレンド
[デザイン]消費者ニーズに応えて進化するデザイン
[ワークフロー]印刷に新しい価値を吹き込むオンデマンドサービス
[drupa]drupa2024でデジタル印刷の将来は見えたか
[後加工]受注単価の値上げに取り組み、第3の市場開拓を模索する製本業界
*関連資料 設備投資の動向/フォーム印刷業界
第4章 関連産業の動向
[出版業界]出版市場の動向と読書バリアフリー
[新聞業界]新聞ならではの信頼性を確保しつつ進むデジタルシフト
[広告業界]広告費は過去最高の7.3兆円、インターネット広告は3.3兆円に
[DM業界]ターゲット精度の向上と顧客データの活用・解析でDM効果の最適化を図る
[地域メディア]地域メディアが持つ本質的な効果と事業創出力 派生的効果の包括的評価に向けて
[通信販売業界]通販・EC市場売上高は13兆円超えと成長続く 目立つ老舗カタログ通販企業へのM&A
*関連資料 出版市場/新聞市場/広告市場/通販市場
[コラム]自分を幸せにしてあげていますか?
第5章 印刷産業の経営課題
[サステナビリティ]ビジネスに直結するサステナビリティ サプライチェーン全体で環境対応を考える
[地域活性化]経営資源を活用した地域活性化による企業成長 起業しやすい地域づくりで差をつける
[経営管理]人口が減少する成熟社会の企業経営を考える 経営者に求められる「市場創出」のマインド
[事業承継]未来を見据えたベンチャー型事業承継の提案 自社の経営資源に後継者の意志を融合する
[デジタルマーケティング]デジタルマーケティングはAIマーケティングへ進化、そしてAIインダストリーへ
[AI活用]進化が進む生成AIとAI技術 今後の利活用の鍵は各工程における連携
[労務管理]省力化対応の観点から考える新しい労務管理
[人材]経営戦略とともに捉える人的資本の形成
*関連資料 クロスメディア/AI活用/人材
●巻末資料
DTP・デジタル年表/年表
2000年代の広告を振り返る
印刷技術と素材が生きるギフト商材
9月4日〜6日に開催された「第98回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2024」から、印刷と紙素材を生かしたデザイン製品の出展を紹介する。