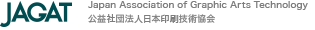本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
本が今の様式になるまで
印刷原点回帰の旅 ―(2)本の発展―
キーワード: 冊 版型 体裁 人間工学 リテラシー 格式
「本とは」と聞かれたとき、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。小説・随筆・実用書といった種類、それとも雑誌・書籍・漫画といった形態、文庫版・A5版といった大きさ、もしくはメディア・情報源といった位置付けなど、人それぞれであろう。一般的に定義するなら、本とは「書物の一種で、書籍・雑誌などの印刷・製本された出版物」のことで、ユネスコによる国際基準では、本とは「表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」である。印刷業界ではB判全紙を16回折ってB5判表裏32ページ以上のものを頁物と呼ぶ習慣があった。
しかしこういった定義を知らなくても、私たちは本が何かを大体知っているし、例えば本屋で手に取った本をパラパラとめくってみるだけで、それが小説なのか実用本なのかぐらいはわかる。本には、その特長によってそれぞれのカタチ、つまり「様式」があって、暗黙のうちに私たちは「様式」を知ったうえで本を活用しているのだ。では何故、本は今のような様式をもつようになり、私たちの生活に浸透していったのだろうか。それを知るために本ができた歴史を、東洋を例に少しだけ振り返ってみたい。
東洋では、1cm程度の幅に切った竹に1行の文章を書いた竹簡というものが生まれ、糸で竹簡を結び合わせた簡冊という文書ができた。これが東洋における本の原形であることは、「冊」が本の単位となっていることからもわかるだろう。糸で結び合わせているので簡冊は巻く形になるが、オリエントでもパピルスは巻物だった。そもそも後戻りできないという言語の特性から文字が生まれ、文書化されたのだから、本には言葉にして読むという前提があったのだ。つまり、読む文章が順に見えていく巻物という形が、本の初めとしては適していたと言える。中には何本にもわたる長い読み物もあったことから、「巻」という単位ができ、本は情報の単位として捉えられるようになった。文明が進み、長い読み物や情報量が増えてくると、どこに何が書かれているかがわかる仕組みが必要になる。新たに発明された紙という材料は折ることに適していたため、巻物が蛇腹のように折られるようになり、やがてより検索しやすいように、半分に折って綴じるような「様式」を本は獲得していったのだ。
しかし、メディアとしての本の普及には、まだまだ時間が必要だった。人間が本を写して作っていたので量が増えなかったと考えられるが、ではグーテンベルクが活版印刷を発明してすぐ普及したかというと、実はそうでもない。『グーテンベルグ聖書』は、所有するにはあまりに大きすぎたし、ドイツで生まれたのにラテン語で書かれていた。印刷術がイタリアに広まっていくとローマン書体の小型活字ができて小型本が作られ普及する。
東洋の木版は大きくなかったが、紙の価格と言うネックがあった。しかし時代を経て科挙の時代になると、試験を受ける人間が古典を覚えるという需要を背景にポケット判のような大きさの本ができる。保管・流通といった観点からもこの大きさにする利点があったが、それよりも読む人間にとって最適な大きさを本が手に入れたことが、その普及の一因を担ったと言える。こうやって、人間工学の観点から見ても普及する「様式」を本は獲得したのだ。
このように振り返ると、本の「様式」が発達してきた歴史は、リテラシー獲得の歴史とほぼイコールと言える。言葉を記録するために文字が生まれ、情報が文章として残され、文字情報である文章を必要に応じてまとめ伝える、といった文化・文明の発展の必然の中で、本は生まれ発展した。この意味において、本は「文字情報の様式化」ということができる。そして現代では、本は更に進化を遂げている。メディアとして用いられることで、本の様式が更に発展したからだ。本の様式とは、具体的には「章・節・項」「前編・後編」といった順序のつけ方や、「目次・はじめに・本文・あとがき・資料・参考文献」といった構成方法、表紙や奥付のような体裁などが挙げられるが、これらの様式が今では逆に文字情報が何たるかを伝える手段になった。本は高度な様式の取得によって、メディアとしての役割を増し、掲載されている情報を格式付けるようになった。そして、文化を先導する大きな担い手となったのである。