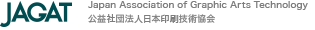本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
凸版印刷におけるCTS開発の経緯<1960ー70年代>
※PAGE20周年記念トークショー「コンピュータ組版の軌跡」より
(元凸版印刷株式会社 専務取締役)
■はじめに
JAGAT主催のPAGE展は1988年に第1回が開催され、PAGE2007まで20年を超す歴史を積み重ねてきた。
20年前というと、PostScript、漢字Talk、PageMaker、Illustrator、LaserWriterなどDTPの中核となるソフト、ハードが次々と市場に登場した時期である。その情勢を背景にして、JAGATは印刷業界における文字処理の変化の動向を示し、それへの適切な対応を促すために最初のPAGE展を開催した。
20年前にスタートしたDTPは、その後目覚しく進歩、発展して現在のIT化、クロスメディア化に繋がったのは、周知のとおりである。
この20年の間に、文字・画像一括処理のDTPによって印刷業界の製版現場は一変したが、従来の活字組版や手動写植から一挙にDTPに置き換わったかというと必ずしもそうではない。
活字や手動写植機による文字組版がコンピュータに置き換わるには、更に20年近く遡るCTS(Computer Typesetting System)や電算写植システムの時代があったのである。
2007年2月7日に、PAGE展の20周年を総括する「コンピュータ組版の軌跡」というテーマでトークショーが開催された。そこで話をした凸版印刷のCTSの開発経過を整理し、その初期段階を以下に記す。
■1960年代、デジタル化の前夜

<富士通の全自動写植システム>(当時の富士通カタログより)
日本経済は1950年代の終わりから1970年代の初めにかけて、岩戸景気、五輪景気、いざなぎ景気と好調に推移した。1960年代はまさに高度経済成長期であり、日本は重厚長大産業の大企業を中心に業績を伸ばし、経済大国への道を辿った。
出版業界、広告宣伝業界も好景気を背景に成長を続けた。それに伴って印刷業界も順調に成長を遂げることが出来たが、一方で「人手不足」という新しい問題が生じてきた。
当時、凸版印刷でも会社の拡張に対応して高校、大学の新卒者の採用に取り組んだ。しかし、新卒者の採用は他業種(鉄鋼、造船、家電、自動車、化学)との競争があり、印刷業としては苦戦を強いられていた。
しかも、折角苦労して採用した若い社員が直ぐに辞めてしまうという事態に直面した。
それは組版職場に配属した若い社員の定着率が、他の職場と較べて非常に悪いのである。活字組版は100年近い歴史をもつ職人集団の職場で、若い社員からは旧態依然とした上下関係の厳しい職場であると看做された。また、鉛合金からくる鉛毒問題のある職場、重量運搬を伴う肉体労働の職場という印象もあった。
さらに、活字組版は技術的には成熟しきった工程で、若い社員に将来の夢を抱かせるような新しい技術が見当たらなかった。そのため若い社員の定着率低下を招いたのであるが、このことは会社の将来にとって極めて深刻なことであった。
出版界では週刊誌、月刊誌の新規発行が続き、百科事典、文学全集、美術全集、辞典類も盛んに刊行された。これらの需要に応えるには文字組版の能力を増やすことこそ必要であって、けっして減らす訳にはいかなかったのである。
そこで1967年に活字に替わる組版方式の調査、研究を開始した。翌1968年、活字組版のコンピュータ化が可能であると判断して組版システムの開発に着手した。
当時、日本語の組版システムを開発していた会社にはIBM、写研、日本電子産業などがあったが、これらのシステムの基本コンセプトは「棒組み」や「箱組み」であった。これに対し富士通のコンセプトはページ単位で誌面を作り上げる「ページ組み」であった。
1969年、凸版印刷は富士通とシステム導入の契約を結び、同時にCTS開発の専任組織を発足させた。
直ちに基本仕様の確定作業に入ったが、検討項目の中に寸法の単位をポイントにするか、ミリメートルにするかがあった。歴史の長い活字組版はポイントであり、当時成長途上にあった写植はミリメートルであった。凸版印刷は、新システムの開発目的が飽くまでも活字組版のコンピュータ化であり、新システムへの移行には得意先の理解が欠かせないことからポイント制を選択した。
また、版面寸法(A4、B5の2系列)、収容文字数(明朝5,826字、ゴシック3,586字、記号類2,876字、計12,288字)、文字サイズ6種(最小6ポイント、最大12ポイント)を確定した。組版ルールを明確にするために、縦組・横組の共存、ルビ処理、割注処理、禁則処理、揃え組み、和欧混植などを詳細に亙って仕様書に纏めた。入力機の漢字文字配列も凸版印刷で決めた。
これらの基本仕様に加え、初校、再校、責了、下版と流れる組版工程が円滑に運用できるように周辺のシステム開発を続けた。
富士通は入力、処理、出力、訂正、再出力のフローに必要なソフト、ハードを全て開発した。入力はF6801A(フルキー方式、紙テープ出力の鑽孔機)、出力はF6531C(回転ドラム字母、枚様感材、フラッシュ露光の光学式印字装置)、処理用コンピュータはF270-20(技術計算用ワードマシン、プログラム言語・フォートラン、アセンブラー)であった。
組版ソフトは、ページ新組と赤字訂正の両機能をもつFCLα2(Fujitsu Composition Language α2)であった。FCLはテキストデータ(文章)とレイアウト制御データを別情報として扱っていた。後になって気づいたが、この機能は版型変更など蓄積データの活用が容易であり、極めて優れた基本コンセプトであった。

<イメージマスタ:ドラム内面に文字母型を収容>(当時の富士通カタログより)
■1970年代、CTSの始まり
凸版印刷は1970年4月に東京コンピュータ(株)という専門会社を設立し、CTSの実用化に踏み切った。主な導入設備は組版処理コンピュータF270-20・2台、入力用鑽孔機F6801A・40台、光学式写植装置F6531C・4台、割付データ入力機4台であった。
これらに加え、14ポイント以上の見出しを印字する手動写植機2台を導入した。この手動写植機は、それまで製造をしたことのないポイント制御の特別仕様のもので、(株)モリサワが製造を引き受けてくれたことがCTSの実用化を可能にしたとも言える。
東京コンピュータ(株)は女性40名のパンチャーを含め、総勢80名の社員で発足した。パンチャー教育は入力キー上に配列された3,000字近い漢字の配列を記憶し、原稿の文字を探し出す訓練から始めたが、実際の仕事が出来るまでには早くて半年を必要とした。1人前になるには更に半年という1年がかりの技能訓練であった。
現在のパソコンで使われるカナ漢字変換システムなどは影も形もない時代のことである。コンピュータへの入力は紙テープであり、写植装置へのデータの受け渡しも紙テープであった。組版の終わったデータの保存には磁気テープが使われた。
これらの作業をするため1台のコンピュータに3名のオペレータを必要とした。東京コンピュータ(株)の現場は入力室、電算室、出力室などに作業員の姿が大勢見えて、CTSはコンピュータが働くのではなく人間が働くという印象の職場風景であった。
6ヶ月以上のテスト、訓練を経て、コンピュータ処理による完全ページ組の第1号が市場に出された。
昭和45年11月1日発行「科学朝日11月号」に『グーテンベルクよ!さようなら――印刷界に進む技術革新――』という5ページの特集記事が掲載された。
これまでベテランの職人が処理してきた月刊誌の組版を、コンピュータの助けがあるとは言え入社6ヶ月の素人集団が取り組んだのであった。僅か5ページではあるが、関係者が緊張して見守る中での初仕事であった。
記事は、「世界3大発明に数えられたグーテンベルクの活字組版に替わってCTSという新しいシステムが登場したことで、今後も印刷が情報伝達の重要な役を担い続けられる」という期待が込められたものであった。この内容は、CTS関係者にとって「お褒めと励まし」の言葉であり、まことに嬉しかった。
しかし、CTSは実用の端緒についたばかりで、その後10年以上続く悪戦苦闘の始まりであった。
活字組版と較べると機能、コスト、納期のどれをとっても問題が多く、早急の改善が要請された。
しかし、当時のコンピュータのレベルでは解決することが難しく、その後のコンピュータ技術の進歩に合わせて順々に改善するしかなかった。
初期CTSの最大の問題点は、正しく組版されたのか、どこかでエラーをしたのかを途中でチェックすることが出来ず、最終の印字処理が終わるまで待たねばならないことである。
印字処理後の文字校正でエラーが見つかると、訂正データ作成、コンピュータ訂正処理、印字処理という作業をしなければならない。1字でもエラーが残っていると再びその作業を繰り返すことになる。
一方、活字組版では組版工が頭と眼と手を使って間違っている活字を取り外し、正しい活字に挿しかえればその場で作業完結となり、余計な時間も材料も使わないで済む。
この問題の解決の武器となるのは漢字ディスプレイであるが、7年後の1977年に導入することが出来た富士通製F6580A(4台端末・1台のミニコン制御・ペンタッチ入力方式)の開発を待たねばならなかった。
1977年当時、F6580Aは1セットの価格が5,000万円であった。端末1台あたり1,250万円相当となるが、当時で3DKか3LDKのマンションが買える価格であった。現在でいうと、4,000万円でワープロ1台を買ったことになる。
富士通にとっては、このような高価な機器がそのまま市場で売れるものではなく、凸版印刷にしてもこのような高価な機器はコストの面から採用できない。
では何故富士通、凸版印刷の両社が無茶とも思える漢字ディスプレイを開発し、採用したのであろうか。それはWYSIWYGの機能をもつ漢字ディスプレイはコンピュータの普及、発展には不可欠なものであり、富士通にとっては避けて通れない基幹商品であった。一方、凸版印刷にとっても活字組版にとって替わるCTSに、WYSIWYG機能の装置は必要不可欠であった。
1台4,000万円のワープロのような漢字ディスプレイを開発し採用したのは、富士通、凸版印刷の各々が自社の置かれた現状を認識し、将来を見通した、夢と覚悟を込めたトップの経営判断であった。
CTSがコスト高であった理由の1つに、漢字の出力方式が感光材料を用いる光学式写植装置に限られていたことがある。実用レベルの普通紙漢字プリンターが使えるまでに8年間待たねばならなかった。
1978年、昭和情報機器製の漢字プリンターSP-7を導入した。それまでの200円/枚の感光紙が、2円/枚の普通紙に変わったのである。100分の1のコストダウンである。さらに、漢字を出力して目で見るという基本機能で比較すると、漢字プリンターの機器コストは写植装置の10分の1であった。
このように普通紙漢字プリンターはCTSのコストを下げる強力な助っ人となった。
1970年に実用化を開始したが、CTSは開発途上にある未完成のシステムであった。それでも生産現場は新規の仕事に挑戦した。
その中で特筆すべきはブリタニカ国際百科事典・全28巻を完成させたことである。これは1971年に着手し、翌72年に第1巻を発刊した。その後、逐次刊行を続け1975年に最終刊を出す5年間の大事業であった。
この仕事を完成させたことでCTSに対する得意先からの信頼感が高まり、生産現場は自信を持って仕事が出来るようになった。
生産現場が次々と仕事を続ける中、技術開発チームはシステムの改善を行った。1973年、富士通から大幅にレベルアップをした組版ソフトFCLα3の提供があった。同時にコンピュータを1ランク上のF270-30に置き換えた。
凸版印刷の開発チームはアプリケーションソフトの開発に取り組んだ。
例えばランダム入稿・配列処理のシステムを開発したが、これは事辞典類の制作期間の短縮に役立った。
活字組版では原稿が五十音順に完全に揃ってからでなければ組版を開始することが出来なかった。原稿が1点でも遅れれば、全体をそれに合わせざるを得なかったのである。
ランダム入稿・配列処理のシステムを利用すると、原稿が出来たら順序に関係なくCTSで組版を始めておいて、五十音に並べ替えるのは最終段階に延ばすことが出来る。そのため原稿段階での待ち時間がゼロになり、刊行物の制作期間の大幅短縮が可能となる。このシステムは名簿制作にも大いに役立った。
また、索引自動作成システム、自動パターン組システムなどを開発し、編集作業、組版作業の合理化を実現していった。
■1970年代後半、自社システム化への取り組み
1970年代の後半になると、凸版印刷は自社による基本システムの開発を手掛けるようになった。これまでの全面的に富士通に頼る体制を脱し、自社技術による独り立ちを目指したのである。
この背景には、富士通がシステム開発の対象を印刷業界から新聞業界へ移行するという事情もあった。
まず、1974年に汎用コンピュータF230-15で稼動する赤字訂正システムを開発し、作業の効率アップを実現した。
続いてTCL(Toppan Composition Language)の開発に着手し、3年後の1977年に汎用コンピュータF230-25を導入してTCLを稼動させた。
この頃になると事務計算用のコンピュータが機能と価格の両面で格段に有利となる傾向が強まり、汎用コンピュータと称されるようになった。したがって、CTSでも科学計算用のコンピュータF270シリーズから汎用コンピュータF230シリーズへ切り替えた。
TCLには基本の組版機能に加えて、多目的情報処理を可能にするタグ機能なども備えた。またページを跨ぐほどの大きな表組みの自動分割機能など、活字組版で出来ることは全てCTSでも出来るようにした。
TCLはバッチ処理型の組版システムとして必要とする機能を殆ど備えたことで、以後30年近く使い続けることが出来た。
印字装置も新しいタイプへの変革があった。1976年、ドイツ・Hell社製のCRT式写植装置を導入したが、印字スピードは20字/秒から100字/秒へと高速化した。この装置で使用するドットフォントも自社で開発した。
1970年代も後半になると、活字部門の縮小を迫られるようになり、作業者を経験と能力によって新しい職場へと移していった。当時は終身雇用制の時代であって、リストラによる退社など考えられなかった。新しい職種への移籍が困難と看做された中高年の作業者をドットフォントの作成作業に当らせることで、一人も退社させずに活字部門を縮小していった。
□■□■□
このような経過を辿りながら、CTSは徐々に完成に近づいていった。
1979年に岩波基本六法の活字組版からCTSへの移行を実現した。岩波書店の編集方針は、長い期間をかけて培った誌面構成は読者への約束であって、CTSへ移すためにマイナスになることは決して認めないという顧客第一主義の姿勢であった。この方針はまことに敬服できるもので、その方針に対応できたことでCTSが完成の域に到達したと判断した。
1979年には角川・日本地名大辞典47巻、講談社・昭和万葉集21巻を完成させた。
また、日本経済新聞の会社情報を新規に発刊した。競争誌である東洋経済の会社四季報は活字組版の機能をフルに活用して制作しており、後発のCTSでは当分無理であると思われていた。しかし、日経新聞の編集部と協力し、専用システムを開発することで遂に実現に漕ぎつけた。
このこともあって、CTSが一人前のシステムあると認知されるようになった。
1980年代になるとCTSの全盛期を迎える。講談社・医科学大事典・50巻、小学館・日本大百科全書・25巻と大型刊行物を相次いで完成させた。
百科事典ブームに対応し、大型の名鑑、名簿、人事録を処理した。
1980年代の中期になるとワープロが実用化され、「ぴあ」の「映画の街角」では通信回線による入出校が実施されるようになった。1980年の後半になるとCD-ROMが市場に登場してきた。そして1980年代の終り近くに、いよいよDTPの登場を迎えることになるのである。
CTSの始まりから定着するまでの経過を1970年代を中心に記述した。1980年代以降の経過は次の機会に譲ることにする。
(2007.5)
※本記事は、2007年5月にJAGAT Webページに掲載したものを再掲載しています。