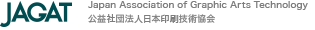本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
原則と応用 【日本語組版とつきあう 3】
組版のルール(原則)をそのまま適用すべき時もあるし、応用すべき時もある。原則と応用という問題は、その適用対象の意味や重要さ、さらに、どの程度の頻度で出てくるかにより扱いを変える必要がある。
組版の原則(ルール)の適用
組版においては、いろいろな要素についてのルール(原則)がある。しかし、このルールには、どの程度そのルールを守ればよいのか、という点で様々なレベルがある。
例えば、行頭に配置してはいけない文字・記号(行頭禁則文字)に句読点と終わり括弧類を含めることは、ほぼ守られている。しかし、小書きの仮名(っょゅィッャなど)、長音記号(音引、ー)、疑問符(?)、感嘆符(!)、中点(中黒、・)、同の字点(々)については、行頭禁則文字に含めない方法も行われている。
それとは別に、実際にルール(原則)を適用する際、そのまま適用すればよいのか、何か工夫を必要としないのか、という問題もある。原則と適用の問題といってよく、実務でも、この原則をどのように適用したらよいか、応用したらよいかの工夫が最も面白いところだと私は考えている。
(そのためには、原則を十分に心得ておくことが必要である。)
行間の原則と応用
行間の大きさは、書籍を例にとると、1行に配置する字数が多い場合、使用する文字サイズの全角アキ(そこに使用している文字サイズと同じサイズのアキ)か、やや狭くするのが原則である。字数が少ない場合、例えば、20字くらいであれば使用する文字サイズの二分アキ(全角の1/2のアキ)までは可能といわれている。
表の行間は表に使用する文字サイズの二分アキ、見出しを折り返した場合の行間は見出しに使用する文字サイズの三分アキ(全角の1/3のアキ)から四分アキ(全角の1/4のアキ)が原則といわれている。
しかし、書籍は1点1点が新製品なので、原稿の内容も分量も見出しなどの構成も、すべて異なっている。実際のケースに応じた工夫が当然に必要になる。
例えば、表の行間はなんでも二分でよいというわけではない。行数が多い表や、版面に入りきらない場合は、行間を狭くする必要が出てくる。
また、表の項目を説明する見出し文字(ヘッダー)の一部だけ特別に字数が多い場合、2行に折り返した方がよく、この折り返したヘッダーの行間は、他の1行のヘッダーとのバランスから、ゼロ(ベタ)にするという工夫も必要である。
適用対象による応用の工夫
この原則と応用という問題は、その適用対象の意味や重要さ、さらに、どの程度の頻度で出てくるかにより扱いを変える必要がある。つまり、適用対象により原則と応用の考え方にも差がでてくる。
書籍を例にすると、本文、見出し、表紙では、応用のあり方、別の言い方をすると個別箇所での例外の扱いに違いがある。
本文は、限られた箇所での例外はあるとしても、基本的には組版の原則を決め、機械的に自動処理を行う。
これに対し、見出しはそれなりの個別処理を行うことができるし、そうした工夫も必要になる。例えば、字数に応じて字間を空ける(字割という)、逆に字間を標準(ベタ組)より詰める(詰め組という)場合もある。
また、表紙のタイトルなどでは、文字単位で文字サイズや字間を微妙に変える、さらに、字形そのものを修正するということもある。
見出しの括弧と句読点
適用対象による扱いに差がある例として、書籍における見出しの括弧と句読点の扱いについてふれておく。
本文上において括弧と句読点は、字幅(文字を配列する方向、字詰め方向の文字の外枠の大きさ)を半角(全角の1/2)と考えると、その前又は後ろに二分アキを原則として保持する。ただし、行の調整処理で、詰められる場合もある。
ここでいう“行の調整処理”とは、行長に不ぞろいが出た場合、指定された行長にするために、括弧や句読点などの約物の前後の字間を詰める、又は漢字や仮名の字間を空けることである。
この行の調整処理も、本文においては原則を指示して自動処理する。
括弧や句読点の前後のアキは、やや空き過ぎに見えて詰めたくなる場合もあるが、行の調整処理などを考慮し、前後のアキを詰めることは一般には行わない。
ただし、パーレンと山括弧(()と〈〉)については、活字組版の時代から、その前後を二分アキとしないでベタ組にすることが一部の出版社で行われていた。
これに対し、見出しに括弧と句読点を配置する場合、文字サイズも大きくなり、これらの前後の二分アキが目立つこともある。そこで、括弧や句読点の前後の二分アキを、四分アキ又はベタ組とする方法が行われている。
四分アキとする方法は一部の出版社の一部の出版物で行われており、ベタ組とする方法もそれなりに行われている。
私は、ベタ組は詰め過ぎと思うので、四分アキにする方法をとっている。柱(ページの欄外に掲げる見出し)や目次でも同様に行っている。
このように、本文ではやや無理があるが、見出しなど限られた箇所では可能となることもある。ケースによっては、原則の応用ということで工夫するとよいだろう。
図1に見出しのパーレンと読点の組方例を、図2に同じ例について、パーレンと読点の前後のアキを示したものを掲げる。

図1

図2