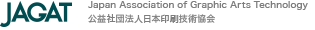本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
小書きの仮名 【日本語組版とつきあう 7】
「ニュース」の“ュ”のように、字面を小さくした印刷文字を小書きの仮名と呼ぶ。
小書きの仮名とは
“あった”の“っ”や“ニュース”の“ュ”のように、字面を小さくした印刷文字がある。これには名前がついているのだろうか。その答は、“JIS Z 8125(印刷用語―デジタル印刷)”にある(この規格では組版用語を多数規定しているので参考になる)。
同規格では、こうした文字に“小書きの仮名”の用語をあて、“拗音、促音、外来語などを書き表す場合に用いる、字面を小さくした仮名”と説明している。また、参考に“捨て仮名、半音ともいう”とある。
捨て仮名や半音(はんおん)という言葉は、以前は普通に使用されていた言葉であったが、最近ではあまり聞かれなくなった。
このように組版に関係する用語には、複数の呼ばれ方をする例がある。括弧類など約物類でも複数の名前で呼ばれる例も多い。組版とつきあうためには、こうしたことに徐々に慣れていく必要がある。
なお,現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示す“現代仮名遣い”では、“拗音に用いる‘や、ゆ、よ’は、なるべく小書きにする”、“促音に用いる‘つ’は,なるべく小書きにする”とあり、必ず小書きにしないといけない、ということではない。
この小書きの仮名の扱いで注意したい事項をまとめておこう。
小書きの仮名に直す方法
校正作業で、普通の仮名(直音を示す仮名)を小書きの仮名に直す(又はその逆)場合、どう指示してよいか迷うものである。
この方法については、“<”や“>”を付けて指示する方法を、2007年に改正された“JIS Z 8208(印刷校正記号)”で規定しているので、それによればよいだろう(図1に例を示す)。

図1:小書きの仮名を修正指示する方法
縦組用と横組用
小書きの仮名は、縦組用と横組用では、ボディに対する字面の位置が異なり、活字組版では別の活字であった。そのために横組の中に縦組用が組まれるといった誤植もあった。
コンピュータ組版では、縦組又は横組と組方向を指示すると自動的に、それに応じた字面が選択される。そのため、小書きの仮名や長音記号(長音記号も縦組用と横組用で字面が異なる)の縦・横混用の誤植を目にすることは、ほとんどなくなった。ただし、表などでは縦組に見えるが、実は横組で処理した場合などもあり、注意が必要である(図2に特別に処理して誤った例と,図3に正しい例を示す)。

図2:小書きの仮名と長音記号が誤っている例

図3:小書きの仮名と長音記号が正しい例
小書きの仮名は行頭禁止か
行頭に配置してはいけない文字・記号を行頭禁則文字という。日本語の組版ルールをまとめた“JIS X 4051(日本語文書の組版方法)”には、“終わり括弧類、行頭禁則和字、ハイフン類、区切り約物、中点類及び句点類が、行頭又は割注行頭にきてはならない”との規定がある。
小書きの仮名は、ここでいう“行頭禁則和字”に含まれており、行頭に配置してはならないことになっている。しかし、JIS X 4051では、別に“長音記号及びよう(拗)促音を含む小書きの仮名を行頭禁則和字からはずすことは、処理系定義とする”との規定があり、小書きの仮名を行頭禁則文字から除外することも認めている。今日の書籍では、禁止としている例は少なく、多くは許容している。
私がこの仕事に関わったころに先輩の校正者から聞いた話では、最初は平仮名の小書きの仮名は、まあ許してもよいだろう、ただ片仮名は許したくない、というルールであった。しかし、平仮名と片仮名の差はどこにあるか、そう大きな違いはないだろうと、すべて許容されていった、ということのようである。しかし、禁止というルールは残り、JIS X 4051でも規定された。
活字組版では行頭禁則を回避する処理に手間がかかることも要因だったが、読書の方法として、直接に声を出さない音読が主になっていったこともあり、行頭に小書きの仮名があってもそれほど読みにくいわけでもない、ということで許容され、それが一般的になっていったと考えられる。
こうしたルールは、何がよいか、どうしたら読みやすくなるか、という面を考慮しないといけないが、習慣や慣れという要素の影響も強い。数多くの本で許容しており、また多くの人が慣れた方法でもあるので、小書きの仮名をいまさら行頭禁止に変える必要はない、と考えてよい。
ルビと小書きの仮名
活字組版のルビ用文字には小書きの仮名は準備されていなかった。コンピュータ組版では、文字を拡大・縮小して使用するので、ルビに小書きの仮名を利用できる。
活字組版でルビに小書きの仮名を使用しないという慣習から、コンピュータ組版でも小書きの仮名は使用しないのが原則とされていた。しかし、最近の書籍ではルビに小書きの仮名を使用する例が増えている。
主な考え方として、次の3つがある。
- ルビは補足的なものであり、そもそもルビの文字サイズはとても小さく、それをさらに小さくした小書きの仮名は、読みやすくないので避けるのがよい。
- 読みやすさに問題はあるが、固有名詞の読み方は、拗促音として読むかどうかが問題となるので、固有名詞に限り使った方がよい。
- 子供向けの本など、拗促音として読むかどうかを示した方がよく、すべてのルビに小書きの仮名を使用するのがよい。
私は、1の考え方に近いが、現在は3つの方法が共存している時代であるといえよう。