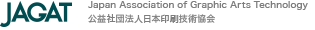本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
売価と原価の微妙な関係
印刷業は受注産業で仕様もロットも1点1点異なるため、原価管理には動的で臨機応変な対応が求められる。
図1はJAGATが実施している「印刷産業経営力調査」における回答企業の平均的な原価構造である。この図の比率を受注一品の原価構造に置き換えてみる。

図1:回答企業の平均的な原価構造
売上が100万円だったとして、材料費や外注加工費など外部に支払う金額が52万5千円(52.5%)。社内の製造経費が25万9千円(25.9%)。全社の管理費と営業販売費が20万円(20.0%)。(営業)利益が1万6千円(1.6%)ということになる。
このままでも利益率は低すぎるくらいだが、仮に競合他社との価格競争が厳しくてさらに値下げを余儀なくされているとして、どこまで値段を下げられるかを考えてみる。
ポイントとなる金額は次の4点が考えられる
- 98万4千円 利益ゼロで収支トントン
- 94万8千円 利益ゼロ、さらに減価償却分をマイナス。減価償却は現金支出を伴わない経費なのでキャッシュフロー上は損しない。
- 74万8千円 2.の金額から販売費と一般管理費をマイナス。いわゆる見積書の営業管理費が0の状態。
- 52万5千円+α 外部に支払う金額から少しでもプラスであればOK
本来は1.、悪くても2.の水準にとどめたいところだが、現実的にはそれ以下で受注するケースもあるし、必ずしも、その判断が間違いだとは限らない。なぜなら、失注してしまえば会社に1円も入らない。社内製造費や販売費・一般管理費は基本的には固定費で、仕事があろうとなかろうと毎月発生する(残業代や電気代など変動費の要素もあるが)。それであれば、多少なりとも固定費が補えれば多少の安値受注をしても受注すべきという考えだ。
図2は、月次なり年次の固定費と加工高(付加価値)の関係を図示したものである。仕事をするたびに、こつこつ加工高を積み上げていって固定費を上回ることができれば黒字となる。収益性重視の戦略だと受注件数(棒グラフの本数)が少なく、棒グラフ間の段差が高くなる。薄利多売だと受注件数(棒グラフの本数)が多くなるかわりに段差が低くなる。
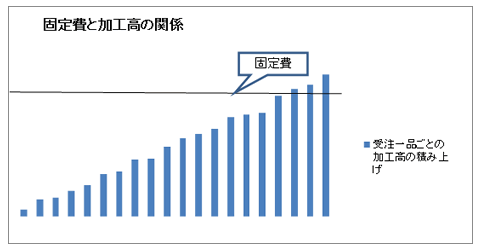
図2:固定費と加工高(付加価値)の関係
いずれにしても固定費を上回れば結果オーライである。この結果オーライというのがやっかいで、印刷機が止まることへの恐怖(印刷人のDNAに刻み込まれている?)もあいまって、ついつい値段よりも受注を優先してしまう。特に新規設備を導入したときには、そのような状況に陥りやすい。けっこう忙しくしているのに決算してみたら赤字。これを前塚田会長 は“合理化貧乏”と呼んだ。
なお、この図は損益分岐点の図と似ているが、損益分岐点の図は売価(単価)と変動費比率が一定であることを前提にしている点が異なる。
図3は、縦軸に受注一点あたりの加工高率(付加価値率)、横軸に受注一点あたりの売上額をとったものである。四角いマスが受注一点を表し、面積が加工高となる。この面積が固定費を上回ればその分が利益となる。
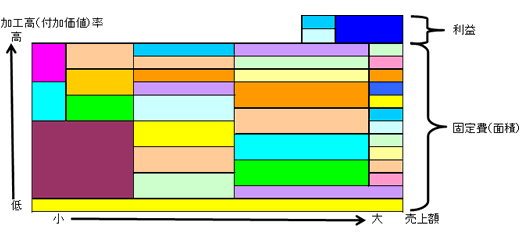
図3:加工高率(付加価値率)と受注一点あたりの売上額
一つ一つの仕事をみると、売上が多いのに加工高率が低いもの、売上は低いが加工高率は高いものなど玉石混交となっている。月次や年次の期間で締めて計算すれば、平均値としての利益率や加工高率は出るが、受注産業で仕様もロットも1点1点異なるのですべての仕事で同じように適用できるわけではない。売上だけを追いかけてもダメだし、付加価値率にこだわりすぎてもうまくいかない。
また、結果としての原価をどんなに精緻に計算してもそれだけでは課題解決には結びつかない。なぜなら価格にしても稼働率にしても印刷会社が主体的にコントロールすることは難しいからだ。印刷会社に求められる原価管理は、もっと動的で臨機応変な対応である。
社長なり営業部長が仕事の入り具合などをみながら、勘と経験を総動員して値段を下げてでも仕事を取るのか、止めるのか、ストップかゴーかを絶妙にコントロールすることが理想ではあるが、それができるのはせいぜい従業員20名くらいまでであろう。30名を超えると勘と経験だけでは限界がある。ましてや受注環境の厳しい昨今ではなおさら難しい。
ではどうすべきか? 営業マン個々人が個人事業主の感覚で自主的に判断できるようにすることが一番の近道ではないかと考える。上司の指示すなわち他律的指示について行動を起こすだけでなく、自主的判断に基づいた自立的な行動もできる社員や組織を育てることである。(これを前塚田会長は“ホロニック社員”、“ホロニック組織” と呼んだ)。
そのために必要なのは、コスト意識を高める社員教育、徹底的な“見える化”による情報共有、そして客観的な数値に基づく評価制度(給与制度)の3つである。
【参考セミナー】
“見える化”実践講座 2013年7月4日(木)開催