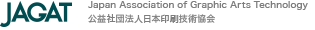本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
ルビの組版 その6 【日本語組版とつきあう19】
グループルビの利用と配置。
グループルビの利用
2文字以上の親文字列に対し、その親文字列全体に対してルビを対応させて配置する方法がグループルビである。
グループルビは、“雑魚”に“ざこ”、“雪崩”に“なだれ”、“無花果”に“いちじく”などといった熟字訓や当て字の読みを付ける場合や、“混沌”に“カオス”、“概念”に“コンセプト”、“大聖堂”に“カテドラル”などの片仮名語をルビとして付ける場合に利用されている。
親文字ごとにルビを対応させることができないルビである。
グループルビの配置方法
複数の親文字列全体に付ける方法としては、次の3つが考えられる。
(1)親文字列もルビ文字列もすべてベタ組とする。この場合、親文字列とルビ文字列の先頭を揃える方法もあるが、一般には、親文字列の中心とルビ文字列の中心を揃える。例を図1に示す。
(2)親文字列、またはルビ文字列をベタ組にした場合の全長を計算し、その長い文字列はベタ組とし、短い方の文字列の字間を均等に空けて、親文字列とルビ文字列の全長を揃える。例を図2に示す。
(3)短い方の文字列の字間を空けるが、それぞれの全長を揃えるのではなく、短い方の文字列の先頭側、および末尾側も空ける。先頭側及び末尾側のアキの量を1とすると、文字列字間のアキの量を2とする方法が一般的である。例を図3に示す。
その他、親文字の字数とルビの字数が同じ場合は、各親文字ごとにルビを対応させることが可能なので、肩ツキの方法で処理する方法もある。中ツキにすると、(3)の方法ということになる。

図1

図2

図3
組版方式とその扱い
活字組版では、グループルビの名称はなかったが、片仮名語のルビや熟字訓・当て字では、親文字列全体に対して配置する方法を行っていた。
ただし、活字組版では、親文字やルビの字間を処理する材料(スペースやクワタ)に制限があったので、字数に応じて前述の3つの方法を適当に採用していた。
例えば、“低音(バス)”は(3)、“情念(パトス)”は(2)、“書字板(タブレツト)”は(1)または(2)といった方法で配置する例が多かった。
コンピュータ組版では、字間を微細な単位で処理できるので、(3)で処理する方法が増えているが、親文字やルビの字数によっては(1)や(2)の方法で処理している例もある。
親文字列からのルビのはみ出し
親文字列よりルビがはみ出した場合は、モノルビと同様に扱う例もあるが、特に片仮名語の場合は、仮名も含め、前後の文字には掛けないという方法で配置する例がある。
親文字列に仮名を含む場合もあり、はみ出したルビを親文字列の前後の仮名に掛けると誤読される恐れもある。
特に(3)の方法で配置した場合、前後の仮名に、はみ出したルビを掛けるときには、親文字列とルビ文字列の配置位置関係を変えないのか、それとも、前後の文字に掛けてよい量を処理した上で親文字列の字間を処理するか、という問題もある。一般には、前者の方法であるが、処理系によっては後者の方法で処理する例もある。
ルビの字数が極端に少ない場合
片仮名語のルビがつく場合、“失われたもの”に対し“ロス”とルビをつけるように、親文字列の字数にくらべ、ルビが極端に少ない例がある。
このような例では、前述のどの配置方法でも、適当な配置にはならない。一般には(3)の方法ということになろうが、この方法では、図4の左の例のように“ロ”のルビは“わ”に、“ス”のルビは“も”の横に配置され、どの範囲の言葉のルビかややあいまいになる。図4の右の例のように、“ロ”のルビは“失”に、“ス”のルビは“の”の横に配置した方がよいだろう。
このような配置方法にするためには、(3)の配置方法に、“ルビ文字列の先頭側及び末尾側のアキは最大でルビ文字サイズで全角(又は全角二分)とする”という制限をつければ解決できる。

図4
行頭と行末の処理
グループルビを行頭・行末に配置する場合、ルビ文字列が親文字列からはみ出したときに、親文字を行頭又は行末に接して配置する必要がない方法では、行中と同じ配置方法で処理できる。
行頭では親文字の先頭を行頭に接するように配置し、行末では親文字の末尾を行末に接するように配置しなければならない、という方針では、親文字列とルビ文字列の配置方法を変更する必要が出てくる。
行頭を例にすると、例えば、親文字列の先頭側は空けないで、親文字列の字間のアキと親文字列の末尾側のアキを同じにする配置方法がある。