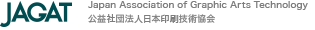本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
「注」の形式と縦組での「傍注」の利用 【日本語組版とつきあう22】
注の目的
日本語の本、特に専門的な本では注記を掲げる例が多い。
引用または参照した出典を示す注記が多いが、注の目的は、それだけに限らない。本の内容によるが、本文解説事項の補足、関連情報、用語の意味・定義、人名・地名の説明などさまざまである。
注の種類
注の目的がいろいろあることから、注の形式も多い。
本文の行に挿入する“割注(わりちゅう)”、段落の間や節・項などの最後に挿入する“後注(こうちゅう)”、横組で版面の下端に配置する“脚注(きゃくちゅう)”、本文を配置する領域とは別に注の領域を確保して配置する縦組の“頭注(とうちゅう)”や“脚注”、横組の“傍注(ぼうちゅう、サイドノート)”などがある。
文中に割り書きしないで、1行で括弧書きの補足説明も、広い意味では注といえよう。また、行間に用語の説明や、古典の現代語訳を掲げる例もある。ごく短い注だけの場合は、版面の下端余白に特別な注の領域を設けないで掲げる場合もある。
日本語の本では、縦組では後注、横組では脚注とする例が多い。
縦組における傍注
横組の脚注に相当する縦組の注が傍注である。ただし、縦組の傍注では、1ページ単位で配置するのではなく、見開きを単位とし、その見開きに出てくる項目の注を、奇数ページ(見開きの左側のページ)の左端に配置する。図1に例を掲げる。
この場合、横組の脚注は、本文の版面領域内に配置するように、縦組の傍注も、本文版面内に配置する。注の分量が多い場合は、それだけ本文の配置も少なくなる。
注形式の選択
注の形式を決める場合、その目的、掲げる内容から判断する必要がある。それ以外に、注の分量も考慮しないといけない。
分量に制限が最もないのが後注である。中には、本文より注の分量の多い本や、1項目で1ページを超える注もあるが、こうした注は後注にした方がよいであろう。
注の多い横組の脚注では、その配置処理にとても苦労する。脚注に対応する本文箇所を変えるなどの工夫を必要とする。
脚注では、できる限り、1ページ内で処理することが望ましい。ほんの一部の注で、次のページに配置される場合は許容できようが、それが続くのは、あまり読みやすいとはいえない。
割注でも、人名などで簡単な説明を加える場合に利用できるが、あまり分量の多い注では採用できない。
本文を配置する領域とは別に注の領域を確保して配置する縦組の頭注や脚注、横組の傍注では、それぞれの箇所で注が平均にないと、ある箇所は次ページにはみ出し、ある箇所では、余白だけが目立つ場合もある。
注は必ず参照されるのか
注の形式を考える場合、その注が読者にとってどのような意味を持つかも考える必要がある。読者は、注を必ず参照するのか、部分的に参照するのか、それともほんの一部だけ参照するのか、という問題でもある。もちろん、参照の程度は読者により異なるであろうが、注の役割を考えた場合にどう考えたらよいか、という問題である。
読者の立場でいえば、注は、すべて読むものではないし、とばしたい場合もあるので、本文を読む流れを疎外しないでほしい。しかし、本文を読んでいると、すぐ参照したい注もあり、その場合には、すぐ近くにあってほしい、というものであろう。あると不都合な場合もあるが、また近くにないと困る、というわがままな願いである。
すぐ近くという意味では割注が最も好ましいが、本文を読む流れが疎外されるというおそれもある。章末または巻末に配置する後注は、本文の流れは疎外しないが、探すのに苦労する。
縦組の頭注や脚注、横組の傍注では、本文の流れも疎外しないし、参照したい場合も近くで探しやすいといえる。しかし、注の配置や分量が平均していないと、余白が多くでたり、同一ページに配置できないという問題が出てくる。
その意味では、横組の脚注は、読者にとっても利用しやすい注である。注の数や分量が多いと問題があるが、DTPなどでも脚注を処理する機能があるので、組版する際にも、比較的に扱いやすい。
縦組の傍注の利用
縦組で傍注を利用した本は、これまではあまり目にしなかったが、明治・大正時代の小説などで、言葉の説明を掲げるなど、最近はやや増えているようにも思われる。しかし、横組での脚注の利用の多さに比べると、まだまだ少ない。
組版ソフトでは、縦組の傍注の自動処理が可能なものが少ない。しかし、本文の流れは疎外しないで、しかも注は近くにあってほしいという目的から考えると、もっともっと利用が増えてよい注の形式であろう。
図1 ※クリックすると拡大します。