本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
ハイデルベルグ社イベントに見る印刷の近未来市場
ハイデルベルグ社は2014年4月2日に世界中から印刷関連記者をドイツ本社に集めて、ハイデルベルグデジタルスニークピーク(Heidelberg Digital Sneak Peek=研究所に忍び込んで新技術をのぞき見する?)と称した新技術及び戦略発表会を行った。
ハイデルベルグ社については今さら説明の必要は無いと思うが、「ハイデルの歴史は印刷の歴史」「印刷の歴史はハイデルの歴史」と言って差し支えない存在の会社である。
ハイデルベルグ市はドイツ南部に位置し、印刷のふるさと的なフランクフルトやマインツ(グーテンベルグ縁の地)などからアウトバーンで1時間、ライン川の支流であるネッカー川沿いに開けた古都である。デュッセルドルフなどよりも小さい街なので、旧市街であるAltstadt(アルトスタット)もこぢんまりとして落ち着いている。
ハイデルベルグ市には有名なものが3つあり、1つ目がハイデルベルグ城で、2つ目がハイデルベルグ大学だ。ドイツで一番古い大学とされており、ノーベル賞受賞者を8人も出しているのはさすがである。おじさん向けにコメントしておくと、大昔、TBS系列の看板TV番組であった「兼高かおる世界の旅」では、ハイデルベルグ市が度々取り上げられていたのをなぜか記憶している。
子供の頃の記憶なので余り自信はないのだが、当時の大学は自治権を持っており、警察も介入できなかったので大学内に牢獄を持っていたというのを、兼高かおるが熱く説明していたのが妙に耳に残っている。今でも公開されているはずなのだが、今回は確認できずじまいであった。

写真1 旧市街から見上げたハイデルベルグ城(この辺には大学施設も固まっている)
3番目がハイデルベルグ社(正確にはHeidelberger Druckmaschinen=ハイデルベルグ印刷機)で、GMのデトロイト(こちらはビッグ3)やKODAKのロチェスターというように、ハイデルベルグ市に住む者は三代にわたってハイデルベルグ社で働く人も少なくない。これも聞きかじった話なので定かではないが、ドイツ国鉄DB(現在は民営化されてドイツ鉄道)が中央駅を作るときハイデルベルグ社を避けるために、わざと線路を曲げて駅を作ったという話まであるそうである。そんな話を裏付けるように、ハイデルの本社は中央駅前の一番良い場所に陣取っている。

写真2 駅前のPMA(プリントメディアアカデミー)ビルと馬のモニュメント(逸話があるらしいが、忘れてしまった。<-アルツ気味?)
4月1日にはデジタルスニークピークの前夜祭としてPMAビルの最上階のレストランでディナーが催された。ハイデルベルグ社の社員バンド(Theオヤジバンドだ)による余興も加わり盛大に行われた。各地や各担当のハイデル社員も混じっているので有意義な意見交換が出来た。
大局的に観てしまうと何処も状況は同じで、インターネットに押されて商業印刷は厳しくなり、パッケージだけが成長市場であるということだった。欧州なので出版に関しての感覚は異なり、北米の電子書籍の迫力に対して、欧州はまだまだ紙が強い印象を受けた。

写真3 ハイデルのシャツを着た社員で結成された親父バンドのサービス付き。しかし、顧客を喜ばせるというより自分の歌いたい曲を歌うのが主目的?
さて本番のデジタルスニークピークは予定通り4月2日に本社裏のR&Dセンターで行われた。ここの地下が工場になっていて、秘密裏にランニングテスト等が行えるようになっている。工場内の写真撮影は禁止なのでご勘弁願いたい。
CEOであるDr. Gerold Linzbachの挨拶の後、記者達は3グループに分かれて秘密地下工場をPeeking(のぞき見)したのだが、今回大きくフォーカスされたのがインクジェットテクノロジーである。良い技術を持った会社とコラボレーションしてより良いソリューションをより早く実現するという方針なのだが、インクジェットテクノロジーに関しては、そんな商品に“Synerjetix”というネーミングが与えられている。コラボレーション相手としては富士フイルムが重要パートナーとして位置づけられ、ジェットプレス720がR&Dセンターの地下工場に鎮座していた。
もうひとつ、ラベル用にGallus社と協同で連帳のインクジェットラベルプリンターを開発していたが、これには富士フイルムのインクジェット技術も盛り込んでいくということであった。この先この2トップでインクジェットマーケットに打って出ようとしているが、バリアブルの能力や柔軟性がどの程度になるか?等、真価を問われるのはこれからである。ハイデルの場合は総合的なメリット、つまりポストプレスシステムのシステム化、アナログ印刷やデジタル印刷が総合的にワークフローに組み込まれることなどが実現されれば、商品力は増すことは間違いない。
市場的な見地でのハイデルらしさといえば、この先の近未来市場に対してハイデルはこう考えていることである。もっとも生産性の高い方式はオフセット印刷で、生産性を犠牲にせずにフレキシビリティを求める顧客にはAniColorを用意しているということで、見学者が通りかかると気楽にAniColorを動かし、5枚毎の色調変化がいかに少ないかを見せていた。
このところ欧州でもやっとUVが注目されだしたらしく、個人的にはAniColorとの相性(市場性)は悪くないと思うのだが、いかがなものだろうか?短時間で刷れるAniColorには乾燥時間がない方が良いに決まっているというという単純な発想だが。
それより小さいロットにはデジタル印刷で対応していくことになる。トナー機のライノプリントは小ロットに対して、フレキシブルな対応も含めて処理していくということである。そして今回は、もう少しロットの大きいものに対してはインクジェットで対処するということで、富士フイルムとのコラボ商品をHeidelberg Jetmasterとしてラインナップしている。
またこの分野にラベルプリンターを用意してきたのには「ハイデルよ、お前もか」的に、やっぱりパッケージ・ラベルかということを再認識させられた次第である。オフセットの主力工場であるハイデルベルグ郊外にあるWieslosh-Walldorf工場の一番新しいホールもパッケージ対応の機械ばかりであり、印刷市場の変化が肌で感じられる。
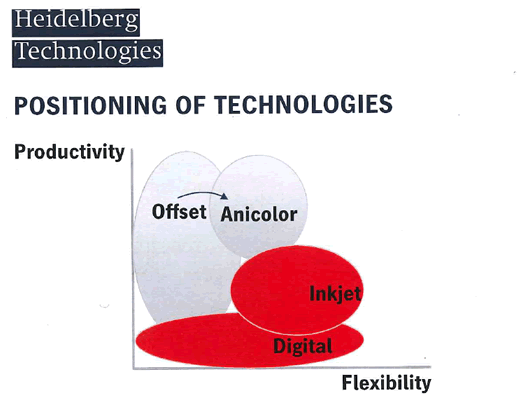
図:市場の4分類
個人的に一番興味を引いたのが4Dプリントと呼んでいる立体印刷機だが、要するにサッカーボールに印字したり、車だったり、ビンやペットボトルに印刷できるというインクジェットベースの印刷機である。ハイデルらしいのは印刷も出来るし剥がすことも可能で、再利用OKということであった。
現在はラベルを貼ったり、シュリンクしたりしているが、直接印刷ということが可能だったら直接を望む方も少なくないはずだ。この手の需要は今後かなり増えていくことが予想されることは間違いがない。

写真4 R&Dセンター

写真5 講演者の3人(右からLinzbach CEO、Oliver氏、Plenz役員)

写真6 熱気のある会場風景
このあとCEOのLinzbach氏がハイデルのストラテジーを語った。つまり「独りよがりにならず、良いモノをいち早くソリューションとして採用していきますよ」ということである。また役員であるStephan Plenzがハイデルユーザーの状況やデジタル印刷でコラボするパートナーについて説明した。そしてJason Oliver氏がデジタルストラテジーについて熱く語ってくれた。
とかくドイツの会社は我々の考えるストラテジーが一番であり、顧客はそれを実行すれば上手くいくというイメージが強かったが、今回のイベントではデジタルストラテジーを手伝ってくれるコンサルタントを紹介したり、上手くいっている会社を紹介してより上手くいくようにしましょうなど、協力体制でソリューションをより完成に近づけましょう的なイメージが強く、「ハイデルも変わっていくぞ!」的な気持ちは強く感じ取れたと思う。少し長くなってしまったので、今回は一旦筆を置くが、2弾3弾の報告は会報誌『JAGAT info』等も含めてお約束する。
(JAGAT研究調査部長 郡司秀明)
