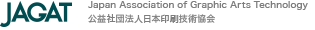本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。
和文フォントデザインの基本(1) (2000/2/18) フォントデザインの実際(3)
和文フォントは、原則として漢字・平かな・片かなのボディは全角(正方形)である。活字の場合は固定ボディというが、写植やデジタルフォントでいう仮想ボディである。しかし「字面(じづら)」は仮想ボディの内側にデザインされる。これを「実ボディ」という。
この書体デザイン上の基本要素としては、
(1)仮想ボディと字面の比率(字面率)
(2)漢字とかなの比率
(3)線の太さ
などが大きな要素である。
どの書体でもデザインをするときには、まずデザインする書体の設計思想(デザイン・コンセプト)を確立する。そして仮想ボディ内の漢字とかなの大きさの比率を決める。(図参照)

次に、適用範囲(本文用か見出し用か)により、縦線・横線の太さや各エレメント(点・ハライなど)の形を考える。本文用書体(ボディタイプ)は可読性を重視し、見出し用などのディスプレイタイプはビジュアル性を重視する。
これが書体デザインの基本であり、これによってフォントの品質が左右される。
活字時代のフォント
活字というと金属活字を連想するが、活字といえば印刷用文字の代名詞である。活字にフォントの言葉はおかしいが、文字処理システムの変遷にともない新しい呼称が生まれ区別されるようになった。活字組版用を「金属活字」というならば、写植機用の文字は「写植活字」といえるし、現代のデジタル文字は「電子活字」といえる。つまり処理方式により文字デザインや制作方法が異なるからだ。
活字時代の文字には、書体デザインとかフォントデザインいう言葉は使われなかった。活字は母型から鋳造して造られるが、その母型制作に先人達は多くのエネルギーと時間を費やした。母型制作は、手工芸的に黄楊(つげ)の木に種字(原字)を彫刻することから始まる。しかも文字を逆向きに彫るわけで、まさに名人芸である。
判子屋さんも同じようにみえるが、印刷用活字の場合は数千字が揃っていなければ使い物にならないことが大きく異なるところだ。この種字を基にして電胎母型が造られるわけで、種字の良し悪しが活字の品質を左右することになる。
この手工芸的な母型制作に代わり、母型量産化のために1920年頃米国から「ベントン彫刻機」が導入された。米国では父型彫刻用に開発されたものであるが、母型彫刻に応用された。しかし、1940年頃まではそれほど活用されなかった。
1949年以降になり、国産の母型彫刻機が大手印刷会社や母型メーカー、活字販売会社などに普及し、母型の量産化が始まった。
この母型の機械彫刻が活字デザインと活字品質の向上に大きく寄与した。この方式はパンタグラフの原理を応用したもので、1つのパターン(原字)から大小の母型が彫刻できることが特徴である。この原字制作方法は、紙の上の50mmあるいは2インチ角に鉛筆でデッサンし、そしてカラス口と定規や雲形定規を使い、あるいは部分的にフリーハンドで墨入れする。つまり原字版下である。この方法は現在でも、デジタルフォント作成のデザイン手法としても用いられている。